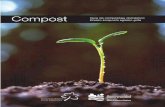%Ê'2(Ö0[ '¨>/>7>. 522° M*ñ%Ê'2å±î - Kushiro · 2020. 4. 20. · ¦ [>5 âu"@_6õm ºÛÈÝ...
Transcript of %Ê'2(Ö0[ '¨>/>7>. 522° M*ñ%Ê'2å±î - Kushiro · 2020. 4. 20. · ¦ [>5 âu"@_6õm ºÛÈÝ...

研究紀要 第190号
釧路教育研究センター


【目次】
発刊にあたって 釧路市教育委員会教育指導参事 大山 稔彦 ………………………… 1
生徒指導研究専門委員会委員長 春名 健司 ………………………… 2
はじめに …………………………………………………………………………………… 3
第1章 理 論 編 Ⅰ 生徒指導とは ………………………………………………………… 5
Ⅱ 生徒指導の意義 ………………………………………………………… 6
Ⅲ 生徒指導の具体 ………………………………………………………… 8
第2章 アンケート編 「初任段階教員に聞いた生徒指導の実際」 ………………………………11
第3章 事 例 編 コラム 「教育的視点と福祉的視点」………………………………………17
事例1 忘れ物の多い児童生徒への対応……………………………………18
事例2 クラス替え当初の集団づくり………………………………………20
事例3 教師が見ていないところで起きた子供同士のトラブル…………22
事例4 グループづくりに関するトラブル…………………………………24
事例5 学習発表会などの行事における配役決めに関するトラブル……26
事例6 適切な初期対応で防止が可能ないじめのケース…………………28
事例7 持ち物に関するトラブル……………………………………………30
事例8 問題行動に対する対応と信頼関係づくり…………………………32
事例9 家庭環境の改善が必要な児童生徒への対応………………………34
事例10 様々な要因が複雑に絡み合っている不登校のケース……………36
事例11 スマートフォン・携帯電話に関するトラブル……………………38
事例12 組織としての対応……………………………………………………40
事例13 関係機関との連携……………………………………………………42
コラム 「集団づくり」………………………………………………………44
巻末資料 相談窓口一覧 …………………………………………………………………45
さわやか学級・青空学級 ……………………………………………………46
釧路市ふれあい教室 …………………………………………………………47
スクールソーシャルワーカー(SSW)活用事業 ………………………48
おわりに 生徒指導研究専門委員会副委員長 熊谷 亮太

1
発刊にあたって
釧路市教育委員会 教育指導参事 大 山 稔 彦
教育界では,その時々で使われた多くの言葉が消えていく中で,不動の
地位を築いている言葉がこの「生徒指導」です。そのため「生徒指導」と
聞いてイメージするものは教員として過ごした環境や時代を反映してお
り,その内容は「竹刀」や「黒板用定規」,「校則」,「生徒玄関」など様々
ではないでしょうか。私の世代は,中学校の廊下を自転車が走り牛乳パッ
クが飛び交った時代なので「生徒指導=荒れた学校」のイメージでした。
対処療法ばかりだった当時,予防に重点をおいた「積極的な生徒指導」と
いう言葉を新鮮に感じたことを思い出します。
今の時代は,児童生徒の抱えている課題が多様化・複雑化し学校のみで
完結できる事案は少なくなり「生徒指導=関係機関」というイメージでの
対応が主になります。これは特別支援教育の対応と共有した部分が多く,
両方共に,児童生徒を丸ごと受け止めて社会との共生を図る営みと言えま
す。
ですから,今まで以上に学校の役割がスリム化し,関係機関との連携の
窓口となるコーディネーターの役割が重要になっており,各学校には組織
の再編と専門的な知見を備えた人材の育成が急務になります。加えて,全
教職員で児童生徒理解を深め望ましい人間関係を醸成するとともに学び
に向かう集団づくり等を進めることが必要になります。
このような中,生徒指導研究専門委員会が,今の時代に合わせた「生徒
指導ハンドブック」を作成しました。各学校において,若い教員には「今
求められている生徒指導の基礎基本」として手元において活用するように,
経験年数の多い教員には「チームとして取り組む生徒指導の指針」として
必ず目を通すようにご指導願います。そして管理職には学校経営の中核に
「自己指導能力の育成」を位置付けたり,保護者や地域住民,関係機関と
の信頼関係を築き円滑な連携を図ったりするなど,チーム学校としての具
体的な取組をお願いします。
また,不登校やいじめなど緊急性の高い事案への対応の遅れは,発生時
の学校側の先入観や思い込みなどの事実誤認による場合が多いので,本紀
要の事例編を参考に常に頭を柔軟にして判断を誤らないよう努めてくだ
さい。
結びに,本研究の推進にあたり,お力添えをいただきました関係各位を
はじめ,2か年にわたり熱心に調査研究活動に取り組まれた担当研究所
員・研究専門委員の先生方のご苦労に心から感謝を申し上げ,研究紀要発
刊にあたっての挨拶とします。

2
発刊にあたって
生徒指導研究専門委員会
委員長 春 名 健 司
かつて輝かしい未来として想像された21世紀を迎え,もうすぐ20年が経とうとし
ています。教育の立ち位置は今,どうなっているのでしょうか。
先日,植松電機(赤平町)社長の植松努さんのブログを読む機会がありました。
「(前略)学級崩壊などが話題になっていますが,じゃあ,幼稚園で学級崩壊ってして
るのかな?僕が知ってる範囲では,年長さんはかなり大人です。しかし小学校に入った
とたん下っ端扱いされて,命令と強制されて,急激に幼児退行が進む子が目立ちます。
(後略)」
もちろん,小学校でしっかり指導されている先生方の存在を認識された上での植松さ
んの意見です。このブログの中で植松さんは,学びにおける『主体性』の大切さを取り
上げています。
教育には時間が必要です。目に見える変化を早急に求める教育は,実を伴わないもの
となります。目の前の児童生徒としっかり向き合い,対処し,働きかけ、待つことが,主体
性を培っていくことにつながり,学習指導,生徒指導,双方において,児童生徒が自ら考
え,行動するための指導が求められています。もちろん,即時的な対応が必要な事態も教
育現場では起こります。そのため,学校では組織的な対応や,関係機関との連携がこれ
まで以上に必要となり,様々な方法で児童生徒に働きかけ,心を動かす指導が大切になっ
ています。
「先生とは,『先を生む』仕事」。教師には,これからの未来を歩む児童生徒に,先
を生む資質・能力や自己指導能力を育むとともに,それらを支える主体性を培うことが
求められています。
複雑化・多様化する現代社会において,児童生徒は変化の激しい状況の中で学校生活
を送ることになります。このような状況だからこそ,児童生徒・保護者と直接向き合う
我々教師の役割の大きさを実感しています。
この教職に誇りをもち,児童生徒にとって最後まで“信頼できる大人”でいられるよ
う,諸課題と真摯に向き合っていきたいところですが,完璧である必要はありません。
教職員がチームとなり,組織力を上げていくこと,先輩方の経験に学び,見聞を広げ,
予測と予防に努めていくことが大切だと考えます。児童生徒が希望ある未来を想像・創
造できるよう,辛抱強く育て支えていくためのヒントが本研究紀要には詰まっています。
ぜひご活用ください。
筆末になりましたが,本研究にあたり,多くのご指導,ご助言,ご協力を賜りました。
お力添えいただいた皆様に心より感謝申し上げ,発刊にあたっての挨拶といたします。

3
はじめに
Ⅰ 学校教育に求められているもの
「知識基盤社会」の到来や,グローバル化,情報化,少子化,高齢化,社会全
体の高学歴化等を背景に,社会構造の大きな変動期を迎えており,変化のスピー
ドもこれまでになく速くなっています。
したがって,既存知の継承だけでなく,未来知を創造できる高い資質・能力を
有する人材を育成することが,極めて重要な課題となります。
また,児童生徒に視点を向けると,一人一人が自ら考え,行動していくことの
できる自立した個人として,心豊かに,たくましく生き抜いていく基盤を培うこ
とが重要となります。
これからの学校は,児童生徒の知・徳・体にわたるバランスの取れた成長を目
指し,保護者や地域住民と協働しながら,活気ある教育活動を展開する必要があ
ります。
Ⅱ 今を生きる教師として 教職は,日々変化する児童生徒の教育に携わり,児童生徒の可能性を広げる創
造的な職業です。社会状況が急速に変化し,学校教育が抱える課題も複雑化・多
様化する現在,教員には,最新の専門的知識や指導技術等を身に付け,常にアッ
プデートしていく姿勢が重要となっています。
一方で,働き方改革が叫ばれる昨今,学校には多くの役割を担うことが求めら
れており,それにより児童生徒への総合的な指導が可能な反面,役割や業務の際
限が見えない側面もあります。学級担任による個の対応としては,限界があるの
が現実です。
このような状況の中では,学校における業務の進め方や校務分掌の在り方,連
携の在り方を適宜見直し,関係機関等との連携も視野に入れて,様々な課題の解
決に当たることができる「チームとしての学校」体制を構築することが必要です。
個々の教員・関係機関が有する多様な経験や専門性を,学校現場でチームとして
最大限に生かしていくことが,今後ますます重要となります。
Ⅲ 本書の活用にあたって
本書は,第1章「理論編」,第2章「アンケート編」,第3章「事例編」で構成
し,具体的な生徒指導の場面に焦点を当ててまとめました。理論と事例がつなが
るよう互いのページに注釈やコラムをつけたり,索引を設けてキーワードを重視
したりすることで,少しでも日々の実践に生かしていただけるようにしました。
学級経営についての事例については,釧路教育研究センター研究紀要第183
号にまとめています。ぜひそちらもあわせてご覧ください。
社会構造の大きな
変動期
未来を創造できる
人材の育成
保護者や地域住民
との協働
最新の専門的知
識・指導技術等を常
にアップデート
多様な経験・専門性
を生かしたチーム
としての学校
具体的な生徒指導
の場面に焦点化
注釈・コラム・索引

第1章
【理論編】
Ⅰ 生徒指導とは
Ⅱ 生徒指導の意義
Ⅲ 生徒指導の具体


5
Ⅰ 生徒指導とは
「生徒指導」と聞くと,問題行動に対する指導を思い浮かべる場合が多いかと思います。しかし実際
には,児童生徒がより良く育つように働きかける教育活動全般を生徒指導と言います。よって,児童生
徒を育てるのは学校に限らず,また生徒指導の範囲も非常に広いものとなります。
児童生徒のより良い成長を考えるとき,我々教師が広い視野で物事を捉え,児童生徒や教師自身の日
常を大切にすることが,非常に重要になると言えます。
コラム 〜 児童生徒が育ちにくい現実 〜 ■現代の課題
○人間関係を作る力の低下 ○耐性の低下 ○規範意識の低下 ○自己肯定感の不全
【Topic1】「価値観や社会的スキルは自然に身に付くもの」という考えは通用しない時代
→「学んでいないこと」は,学習する場がなければ身に付けることが難しい
【Topic2】「心のエネルギー(心理的安定)」と「社会的スキル(人とかかわる能力)」の不足
→困難を抱える児童生徒は,何らかの理由で両者が育っていない状態 →問題行動として表出することも
■児童生徒が育つために必要なもの
・児童生徒が人間関係を育てる「場」の創造
・育ちを支えるサポート体制の再構築
現代における生徒指導の役割の大きさを考えさせられます。学校が,家庭や社会と積極的に関わり,育
てる生徒指導を地道に行っていくことが大切です。
(平成29年度研修講座「アセスデータの読み取りとその活用方法」資料より)
生徒指導とは,一人一人の児童生
徒の人格を尊重し,個性の伸長を
図りながら,社会的資質や行動力
を高めることを目指して行われ
る教育活動のこと。
(生徒指導提要)
生徒指導とは
社会の中で自分らしく生 きることができる大人へと その成長・発達を促した り支えたりする意図で の総称
(国立教育政策研究所「生徒指導リーフ」)
が
児童生徒を育てるのは…,
児童生徒自分自身であり
家庭であり,
学校・教師であり,
社会・関係機関である。
多くの関わりが,多くの種を蒔き,多面的・総合的に児童生徒を育てる。
家庭

6
Ⅱ 生徒指導の意義
生徒指導の積極的な意義は,
現在及び将来
における を図っていくための の育成を目指すこと。
(生徒指導提要)
つまり,
と思い続けられる児童
生徒を育てること
と言い換えることができます。
人は,自己選択・自己決定を繰り返し,
時に成功し,時に失敗しながら成長して
いきます。児童生徒についても,発
達段階相応に有する万能感を,様々
な経験を経て現実を知ることを
通して,少しずつ消失していき
ます。
稚拙ながらも自己選択と自
己決定を繰り返し,目標に向
かって努力したり,結果
を受け入れたりして自己
実現に向かいます。
その根本には,「より
良くありたい」(自己肯
定感),「社会の一員と
して認められたい」
(承認欲求)という
思いがあります。こ
うした思いを胸に,
目標に向け主体的に方向付けて
いくために求められている能力
が自己指導能力です。
我々教師は,児童生徒の自己指導能力を育むことを大事にし,適切な指導・援助を行うことが求めら
れます。問題行動への対応も,自己指導能力を育む大切な一場面と捉えることができます。
「より良くありたい」
将来
現在 指導・援助
指導・援助
より良くなりたい
より良く生きたい
より良くありたい
社会(集団)の一員として
認められたい
自己選択・自己決定 よく考える
→選択・決定する
→努力する
→・成功体験
・不本意な結果を受け入れる
→・周りの人や物に及ぼす影響を考える
・周りの人や物からの反応を考える
自己選択・自己決定
自己選択・自己決定
自己実現
自己実現
自己実現
指導・援助
自己実現 健全な人間は,人生に究極の目標を
定め,その実現のために努力する存在
である。
クルト・ゴルトシュタイン
カール・ロジャーズ
万能感 心理学用語で、「自分が何でもできる」という感覚を意味する語。
特に子供の発達段階において、しばしば見られる現象である。自身の能力を過大評価してこの感覚を持つことによって、対人関係などに問題が生じる場合もある。全能感とも言う。

7
自己指導能力を育成するということは,自らの人格の完成を自ら希求
する児童生徒を育成するということであり,非常に困難な課題と言えま
す。教育の方法として,「与える」,「導く」,「型にはめる」などの方法を
そのまま用いたのでは,自発性や自主性を強要するということになりか
ねず,本来の意味での自発性や自主性を育むことはできません。
学校教育の場においては体系性や計画性が求められ,あらゆる行動や
活動を児童生徒に決定させていくことは不可能です。しかし,指導の中
で児童生徒が主体的に取り組めるような配慮を行うことで,自発性や自
主性,自律性を育んでいくことが可能になります。自ら進んで学び(自
己学習力),自ら問題を発見し(課題発見力),自ら解決しようとする力
(課題解決力)が育つ指導を行っていくことが望まれます。
より良くなりたい
より良く生きたい
より良くありたい
○一人一人は,何ものにも代え難
い存在であるという認識に立
ち指導する。
○有用感(所属する集団から自分
は必要だと思われる),有能感
(自分はこんなことができ
る),成就感(「できた」「わか
った」)を味わえるようにする。
○相手の立場で,相手の気持ちを
理解し,互いの人格を尊重する
ことができるようにする。
○教師は,児童生徒を受容し,児
童生徒がお互いに認め合い,支
え合うことができるような温
かい雰囲気づくりに努める。
○自らの行動を選択・決定,実行
させ,責任を取る場や機会を与
えることによって,自らの可能
性について自信を確かなもの
にしていくことができるよう
にする。
自己指導能力育成の3要素
コラム〜「社会人基礎力」3つの能力と12の能力要素〜
経済産業省が主催した有識者会議に
より,職場や地域社会で多様な人々と仕
事をしていくために必要な基礎的な力
を「社会人基礎力(=3つの能力・12
の能力要素)として定義されたものが右
図です。
自己指導能力と重なる部分も多いの
ではないでしょうか。
自己指導能力 児童生徒が自己実現に向
けて、自らの目標を明確に
し,その目標の達成に向けて
自らを主体的に方向付けて
いくために求められる能力 ※ MLA(マルチレベルアプローチ:包括的生徒指導)より
社会(集団)の一員として 認められたい
三次的生徒指導 …………教員や専門家の力を添える
二次的生徒指導 ………友だち同士支える力を育てる
一次的生徒指導 ……自分の力で解決できる力を育てる
自己指導能力

8
Ⅲ 生徒指導の具体 学校が担う生徒指導では,以下の2つの視点で考えることを
大切にする必要があります。
(1)生徒指導はいつでも (2)生徒指導は広い
(1) 生徒指導はいつでも
生徒指導は,以下の2つの場面に大別されます。【図1】
① 日常場面 【予防的で日常的な指導】
・コミュニケーション ・ノンバーバル コミュニケーション
・ルール ・隠れたカリキュラム ・組織的な対応
② 非日常場面【具体的な問題行動への対処的な指導】
・情報の精査 ・組織的な対応 ・ピンチをチャンスに
(2) 生徒指導は広い
生徒指導は,その性質上,教育課程の範囲に限らず機能していま
す。したがって,児童生徒に働きかけていくのは学校だけではなく,
家庭であり,関係機関でもあります。多面的に児童生徒を捉えるた
めに,様々な人や関係機関と協力していく必要があります。【図2】
コラム〜 隠れたカリキュラム 〜 日常を大切にすることに関わって考えたいのが「隠れたカリキュラム」
についてです。隠れたカリキュラムとは,「教育する側が意図する,しな
いに関わらず,学校生活を営むなかで,児童生徒が自ら学び取っていく全
ての事柄」のことです。教師の心ない言動や意図のない振る舞いは,負の
メッセージとなって児童生徒が学び取っていく可能性があるのです。
日常的な学級経営について
は「平成27
年度新・学級
経営ハンドブ
ック」をご参
照ください。
社会教育
家庭教育
学校教育
教育課程内 教育課程外
学習指導
生 徒 指 導
【図2】生徒指導のイメージ②
生徒指導
日常 成長,発達を促進する。
非日常 現実的な問題解決を図る。
開発的・予防的
【図1】生徒指導のイメージ①
対処的
児童生徒理解 望ましい
人間関係づくり 学校全体で進める
生徒指導は,教育課程内にとどま
らず,休み時間や放課後等に行われ
る個別的な指導や,学業の不振な児
童生徒のための補習指導,随時の教
育相談など,教育課程外の教育活動
においても機能する。
(生徒指導提要)
日常的には…,
○ 共感的理解で信頼関係を育む。
○ 集団生活で規範意識を育む。
○ 共感的な人間関係を育む。
○ 個と集団を育てる。
具体的な場面では…,
○ 事実確認(情報収集)をする。
○ 優先順位を的確に判断する。
(急ぐのか,じっくり対応するのか)
○ 個への指導・集団への指導。
全体として…,
○ 抱え込まない。
○ 学年・学校として捉える。
○ 保護者の力を借りる。
○ 関係機関と連携・協力する。
生徒指導の3本柱

9
児童生徒がよりよく育つように働きかけていくことが生徒指導であるならば,
児童生徒にそれらの働きかけが受け止められることが大切です。
その基盤となるのが,児童生徒が「自分は大切にされている」と感じられるよ
うな教員の児童生徒理解です。児童生徒理解を深めるには,それぞれ異なる個を
認め,客観的に,多面的に,総合的に理解することが大切であり,一人一人の言
葉に耳を傾け,その気持ちを敏感に感じ取ろうという姿勢が重要です(共感的理
解)。
また,教員と児童生徒との信頼関係を築くことも生徒指導を進める基盤と言え
ます。その信頼関係をもとに,児童生徒の自己開示も進み,教員の児童生徒理解
も一層深まっていきます。
しかしながら,日常的な働きかけでは心を開かない児童生徒,指導が響かない
学年・学級があるのも現実です。児童生徒の気持ちが開いていなければ,指導し
ても効果は当然薄いものとなります。具体的な場面や出来事こそ,児童生徒が学
び変わろうとしている大切な指導の機会となります(P.10コラム「啐啄同時」参
照)。
たとえ厳しく指導することが必要な場面であっても,当事者である児童生徒が
そうせざるを得なかった背景に寄り添うことで信頼関係が生まれ,自分自身の行
為にしっかりと向き合う契機につながります。また,こうした機会は,教師が児
童生徒のことをどれだけ大切に思っているかを伝えるチャンスでもあります。
児童生徒理解は,教師が児童生徒のちがいを受け入れ,よりよく関わろうとす
る態度にかかっていると言えます。
同じ事実に対しても,ちがう
見方・考え方
思いもちがう
ちがうことを前提として,理
解しようとすることが大切
事例3〔P.22〕
事例7〔P.30〕
「持ち物に関するトラブル」
事例8〔P.32〕
児童生徒理解の深まり
基盤 信頼関係
安心感
自省・内省
教員の
共感的理解
児童生徒の
自己開示
生徒指導の3本柱の共通点
保護者 の思い
教師 の思い
児童生徒 の思い
他者を理解し,よりよく関わる
それぞれちがった 能力・適正, 興味・関心, 生育環境, 将来の希望…
生徒指導の3本柱①【教員⇔児童生徒】
児童生徒理解
事例1〔P.18〕
コラム 〜 信頼関係を形成するには? 〜 ■児童生徒との信頼関係の形成として,以下の5点が例示されています。
●日頃の人間的な触れ合い ●児童生徒と共に歩む教員の姿勢
●授業等における児童生徒の充実感・達成感を生み出す指導
●児童生徒の特性や状況に応じた的確な指導 ●不正や反社会的行動に対する毅然とした指導
(生徒指導提要より)
事実
どちらの方が
児童生徒は
本音を語れる
だろうか?
叱責と傾聴

10
望ましい人間関係づくり
学校教育における日常的で予防的・育成的な生徒指導を考えるとき,集団での
児童生徒相互の人間関係の在り方が,児童生徒の健全な成長と深くかかわってい
ます。望ましい人間関係づくりとこれを基盤とした豊かな集団生活が営まれる教
育的環境を形成することが,生徒指導の充実の基盤となります。
このように考えると,状況に応じて,個別指導と集団指導とを分けて行う視点
が重要です。個別指導とは個を高める指導であり,集団指導とは集団を高める指
導です。個を生かして集団を高めたり,集団の中で個を高めたりするなど,状況
に応じた指導を行うことが大切です。
教員一人一人の努力を生徒指導の目標の達成につなげるには,全教職員の共通
理解を図り,学校としての協力体制・指導体制を築くことが不可欠です。学校が
中心となり,家庭や地域の力を活用できれば,より豊かな生徒指導を進めていく
ことができます。
教師個人の力(マンパワー)に頼り過ぎることなく,学校内外を含む多様な立
場の人間によって組織的に対応することが,児童生徒を多面的・多角的に捉え,
的確に指導・育成していくことにつながります。
事例6〔P.28〕
事例9〔P.34〕
生徒指導の3本柱②【学校⇔児童生徒】
学校全体で進める
学校全体 による 生徒指導 個々の教員の指導
学年・学級経営
学校経営
【集団レベル】
➢ 一人一人に自己存在感を与えること
➢ 共感的な人間関係を育成すること
➢ 自己決定の場を与えること
➢ 自己実現に向けて自己の可能性の開
発を援助すること
【個人レベル】
➢ 自他の個性を尊重すること
➢ 互いの身になって考えること
➢ 互いに協力し合うこと
➢ よりよい人間関係を主体的に形成し
ていこうとすること
事例2〔P.20〕
事例4〔P.24〕
事例5〔P.26〕
事例3〔P.22〕
事例6〔P.28〕
家庭 地域
関係機関
事例10〔P.36〕
事例12〔P.40〕 「組織としての対応」
事例13〔P.42〕 「関係機関との連携」
事例11〔P.38〕
コラム 〜啐啄同時(そったくどうじ)〜 ■学ぼうとする者と教え導く者の息が合って、相通じること。またとない好
機のこと。鳥の雛が卵から出ようと鳴く声〔啐〕と母鳥が外から殻をつつ
く〔啄〕のが同時であるという意から。
事例11〔P.38〕
生徒指導の3本柱②【児童生徒⇔児童生徒】
望ましい人間関係づくり

第2章
【アンケート編】
初任段階教員に聞いた
生徒指導の実際


11
若手教員が生徒指導上,意識していることや困難に感じていることを調査するために,釧路市内の初任
段階教員(採用1~5年目)103名を対象に「生徒指導に関するアンケート調査」を実施した。
校種別内訳 経験年数別内訳
担当別内訳 学級担任90名 担任外7名 その他6名
【 】生活習慣の定着(あいさつ,遅刻,忘れ物など)
【 】学年・学級集団づくり(からかい,当番・係活動,行事の取組など)
【 】児童生徒の問題行動(暴力,悪口,器物損壊など)
【 】児童生徒同士の人間関係(けんか,なかま外れなど)
【 】保護者対応(苦情,無関心,虐待など)
【 】組織的な対応(危機管理マニュアル,教職員間の共通理解,教育相談など)
【 】関係機関との連携(連絡の仕方,打合せの仕方,連携の仕方など)
【 】その他
若手教員にとって生徒指導で困っていることとして,「学年・学級集団づくり」「児童生徒同士の人間関
係」「生活習慣の定着」の3項目をあげる人数が多いことがわかった。【図3】また,校種別で見ると,中
学校では「生活習慣」より「組織的対応」をあげる人数が多いことがわかった。【図4】
小学校 中学校
71 名
32 名
1年目 2年目 3年目 4年目 5年目
25 名 23 名
28 名
22 名
5 名
これまでの生徒指導で特に困ったことについて3つ選び,困った順に
【 】に1~3の番号をつけてください。
0 10 20 30 40 50 60 70
生活習慣
集団づくり
問題行動
人間関係
保護者対応
組織的対応
関係機関
その他小学校 中学校
【図3】生徒指導で困っていること(3つ選択)
問1
(人)

12
【図4】校種別による上位3項目
項目別に見ると,「生活習慣の定着」については,経験年数が増えると割合が減る傾向が見られた。逆
に「保護者対応」「組織的な対応」は経験年数が増えると割合が増える傾向が見られた。また,「学年・学
級集団づくり」は1年目,3年目に割合が高い結果となった。【図5】
【図5】経験年数別生徒指導で困っていること(3つ選択)
小学校
集団づくり
生活習慣 人間関係
人間関係
集団づくり
中学校
組織的対応
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
1年目 2年目 3年目 4年目 5年目
生活習慣 集団づくり 問題行動 人間関係 保護者対応 組織的対応 関係機関

13
経験年数別に見ても各年数で「学年・学級集団づくり」「児童生徒同士の人間関係」「生活習慣の定着」
が上位に位置し,一方「児童生徒の問題行動」「関係機関との連携」は下位に位置している結果となった。
【表1】
【表1】経験年数別生徒指導で困っていることランキング
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位
1年目 生活習慣・集団づくり 人間関係 保護者対応 組織的対応 問題行動 関係機関
2年目 生活習慣 人間関係 集団づくり 問題行動 保護者対応 関係機関 組織的対応
3年目 集団づくり 人間関係 生活習慣 保護者対応 組織的対応 問題行動 関係機関
4年目 保護者対応 人間関係 集団づくり 組織的対応 生活習慣 問題行動 関係機関
5年目 生活習慣・集団づくり・人間関係 保護者対応 組織的対応・関係機関 問題行動
問1では「順位をつけたもので,対応に困った事例について教えてください」という記述欄を設けた。
具体的な事例で多かった項目は以下の通りである。【表2】
【表2】問1の記述で多かったキーワード
保護者対応 22件 部活動関係 3件
集団づくり 14件 特別支援関係
2件
忘れ物 12件 人間関係
登校,遅刻 8件 学び合い
暴力(叩くなど) 6件 整理整頓
SNS,LINEなど 5件 関係機関
指導法 5件 あいさつ指導
組織,共通理解 4件 仲間はずれ,ネグレクト,LGBT
保健室来室,心得,いじめ,習慣づくり
起立性調節障害 各1件
当番,係活動 4件
異性児童生徒の指導 4件
【保護者対応で困った具体的事例(一部)】~そのほとんどが他項目と関連していることがわかります。
子供のトラブル等を保護
者に連絡した際,なかな
か理解を得られない。
早寝,早起き朝ごはんの定着
は,家庭の協力が必要なため
難しいと感じる。
保護者同士のトラブル
子供が納得した話につ
いて,保護者が納得で
きず電話をしてきた。
保護者との信頼関係づくり
保護者への電話連絡が,マイナスな事例ばかりになっ
てしまい,特に問題のない児童の保護者に対して学校
の情報をあまり共有できていない感じがしている。
学校や子供の状況を把握して
いない保護者が多い。
遅刻や忘れ物については,
家庭との連携が大切だが,
その保護者との連携がなか
なかうまくいかない。
教材費未払い,虐待,無関心
親が子供の話を信じすぎて,
こちらの考えを理解してもら
うのに時間がかかった。
言葉遣いの悪い子供に注意したとき,反
抗してきた。厳しく叱責したが,親から
「うちの子そんなに悪い子ですかね」と
クレームが入ったことがありました。
ネグレクトの家庭への対応
(スマホ・携帯は)保護者の
責任の下で使用をお願いして
はいるが,ほとんど管理され
ていない状況。

14
①「あなたは日常的に,児童生徒理解を心がけていますか?」
いつも心がけている 4-3-2-1 まったく心がけていない
②「あなたは対象児童生徒や状況に応じて意図的に指導方法を変えていますか?」
意図的によく変えている 4-3-2-1 まったく変えていない
③「あなたは他の先生方と連携して生徒指導を行っていますか?」
いつも連携している 4-3-2-1 まったく連携していない
④「生徒指導において連携を行ったことのある外部機関(教育委員会・児童相談所など)に○をつけてく
ださい。」
【 】教育委員会(巡回相談・青少年育成センター・ファミリーサポーターなど)
【 】スクールカウンセラー 【 】児童相談所
【 】警察 【 】少年鑑別所
【 】民生委員・児童委員 【 】病院
【 】その他( )
問2では,生徒指導に対する意識について質問したところ,①「児童生徒理解」を心がけている,②「指
導方法」を意図的に変えている,③他の先生方と「連携」しているの回答で4または3に回答した割合が
9割を超えていた。このことから,若手教員が「児童生徒理解」「指導方法」「連携」について日常的に意
識して生徒指導をしていることがわかった。【図6】
【図6】生徒指導に対する意識について
ご自身の生徒指導についてお聞きします。当てはまる番号に〇をつけて
ください。 問2
0% 20% 40% 60% 80% 100%
4 3 2 1
あなたは日常的に、児童生徒理解を
心がけていますか?
あなたは対象児童生徒や状況に応じて
意図的に指導方法を変えていますか?
あなたは他の先生方と連携して
生徒指導を行っていますか?

15
また,問2では,「①~③で4または3に○をつけた方は具体的に心がけていることを教えてください」
という記述欄を設けた。初任段階教員が生徒指導の際に心がけていること(回答の一部)は以下の通りで
ある。
次に,生徒指導において連携したことのある外部機関として「教育委員会」「スクールカウンセラー」
との連携が多いことがわかった。【図7】
☆小さなことでも(学年主任や管理職などに)報告,連絡,相談をしている。
☆小さなことでも学年の教員と情報を交流し,学年団としての指導を行えるようにしている。
☆生徒指導の際には一人で対応せず,(学年主任や生徒指導部長などに)相談しながら指導にあたるよ
う心がけている。
☆生徒の状況を把握し,諭すべきなのか,話を受け止めるべきなのかを判断し,指導に当たっている。
☆声の掛け方や話す内容,さらには集団の中で指導すべきか個人で指導すべきかを子供や,その時の状
況などによってから変えながら行っている。
☆児童の良いところを見つける視点を常に持ち,ほめるように心がけている。
☆クラスの中でほめてあげたい時に,その子が活躍できる場を意図的に設けている。
☆自分の感情にまかせて子供に接しないように心がけている。
☆必ず理由を聞いたり,事情を聞いたりして,決めつけで指導しないように心がけている。
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
教育委員会
スクールカウンセラー
児童相談所
警察
少年鑑別所
民生委員・児童委員
病院
その他
小学校 中学校
指導方法
組織的対応
☆問題行動や注目行動の裏には,どんな背景があるか汲み取ろうと努めている。
☆児童にいつもと違う感じが見受けられた時は,まず話を聞く。
☆できる限り多くの生徒に話しかけ,関係づくりに努めている。
☆子供との会話の機会を増やすとともに,子供の訴えに傾聴するよう心がけている。
☆メモ帳や座席表を日常的に活用し,子供たちの様子を記録している。
児童生徒理解
【図7】生徒指導において連携を行ったことのある外部機関
(人)

16
以上のアンケートの結果を踏まえて,初任段階教員が生徒指導上で特に困っていると思われる内容を
第3章で「事例編」として取り上げていきます。
「事例編」では,それぞれの事例について,アンケートの項目(生活習慣・集団づくり・問題行動・人
間関係・保護者対応・組織的対応・関係機関)と起こり得る発達段階を表記しています。
「事例編」の構成は,最初に事例の概要を説明し,次に対応の流れをおおよそ時系列で整理しています。
また,できるだけ保護者対応についても触れるようにしています。
「事例編」で示しました児童生徒理解やその対応の仕方はあくまでも一つの例です。各校におかれまし
ては,児童生徒の実態や状況をしっかり見取りながら,本書を参考に生徒指導に当たっていただけると
幸いです。

第3章
【事例編】 コラム 教育的視点と福祉的視点
事例 アンケート項目 発達段階
事例1 忘れ物の多い児童生徒への対応 生活習慣・保護者対応 小学校低学年~中学校
事例2 クラス替え当初の集団づくり 集団づくり・人間関係 小学校低~高学年
事例3 教師が見てないところで起きた
子供同士のトラブル
集団づくり・問題行動
保護者対応 小学校中~高学年
事例4 グループづくりに関するトラブル 集団づくり・人間関係 小学校中~高学年
事例5 学習発表会などの行事における
配役決めに関するトラブル
集団づくり・人間関係
保護者対応 小学校低~高学年
事例6 適切な初期対応で防止が可能な
いじめのケース
人間関係・保護者対応
組織的対応 小学校低学年~中学校
事例7 持ち物に関するトラブル 問題行動・保護者対応 小学校低~高学年
事例8 問題行動に対する対応と
信頼関係づくり 問題行動・保護者対応 小学校中学年~中学校
事例9 家庭環境の改善が必要な
児童生徒への対応
保護者対応・組織的対応
関係機関 小学校低学年~中学校
事例10 様々な要因が複雑に絡み合っている
不登校のケース
保護者対応・組織的対応
関係機関 小学校低学年~中学校
事例11 スマートフォン・携帯電話に
関するトラブル
人間関係・保護者対応
組織的対応・関係機関 小学校中学年~中学校
事例12 組織としての対応 保護者対応・組織的対応 小学校低学年~中学校
事例13 関係機関との連携 保護者対応・関係機関 小学校低学年~中学校
コラム ~集団づくり~ 日常生活の中で「あれっ?」と思う瞬間はありませんか


17
教育の目的は,人格の完成であり,必要な資質を備えた健康な国民の育成にあります(教育基本法)。
一方,児童福祉の原理は,生活の保障であり,子の愛護にあります(児童福祉法)。教師はその両方の
視点をもち,児童生徒の背景・生育歴等も含め,対処していくことが求められます。
教育的視点では,諸課題に対し,児童生徒が粘り強く物事と向き合ったり取り組んだりする姿勢を大
切にします。その根底には,「本質から逃げず,困難を乗り越えたり,解決する力を付けたりして,大
きく成長してほしい」という願いがあります。一方,福祉的視点では,諸課題の原因がどこにあるとし
ても,生活の保障を大切にします。その点では,「本人にはどうしようもない状況などは当然起き得る
ことであり,そうした時には避難することや時間を置くことも有効な手立ての一つ」という考え方もで
きます。
学校現場では,この2つの視点が交錯する事案がしばしば起きます。ですから,我々は,児童生徒に
働きかけ,話を聞き,それらを見極めていくことが求められます。教育的視点をもちながらも,状況や
様子を見て,福祉的視点に切り替えていくことが大切です。
『学校不適応』を例にとると,「教室に入れない(結果的に『入らない』)」「学校に行けない(結
果的に『行かない』)」「友達に会えない(結果的に『会わない』)」ことなどには,多大なエネルギ
ーを必要とします。もちろん,『わがまま』や『甘え』という可能性もあります。しかし,どちらにし
ても,こうした不適応を乗り越えるためには,それを超える大きなエネルギーが必要となります。その
エネルギーこそ,保護者や教師などの大人からの働きかけや,児童生徒自身の気付きから生じるものな
のではないでしょうか。『わがまま』や『甘え』であれば,それに気付かせる手立て・指導が必要であ
り,一方,『学校不適応』であれば,凍った心を解かすような手立てや支援,または,不適応の原因が
どこにあるのかを多面的に考察する手立てや支援が必要です。そうした丁寧な働きかけが児童生徒の内
省につながり,少しずつ心のエネルギーが充足されていくのだと考えます。
我々教師には,児童生徒の様子,環境,状況をつぶさに捉える努力をし,見極め,対応していくこと
が求められています。「教育は人なり」と言われる所以は,そこにあるのではないでしょうか。
コラム
~教育的視点と福祉的視点~
日常のエネルギー 非日常のエネルギー
友達と会う
教室に入る
学校に行く
非日常を変えるエネルギー
友達と会わない
教室に入らない
学校に行かない
みんなが当たり前にしていることをしないエネルギー
当たり前にしていることをする エネルギー
問題の解決を図りながら,目標に迫る。
例)主体性:粘り強さ・自己調整力 など
【主に児童生徒・学級・学校に関すること】
問題の解決を図りながら,生活の保障に迫る。
例)自立支援 など
【主に児童生徒・家庭・障害に関すること】
■教育の目標〔教育基本法〕
人格の完成・必要な資質を備えた健康な国民の育成
■児童福祉の原理〔児童福祉法〕
生活の保障,愛護
児童生徒・家庭
問題行動・不適応をどうとらえるか
甘え or苦しさ
自己中心的 or自己防衛
行動 ⇔ message
非日常を変えるためのエネルギー
【外的要因から】
【内的要因から】 不安
孤独
葛藤
例 例 言葉がけ 環境整備
例
例

18
事例1 忘れ物の多い児童生徒への対応
生活習慣 集団づくり 問題行動 人間関係 保護者対応 組織的対応 関係機関 その他
小学校低学年 小学校中学年 小学校高学年 中学校
対応の流れ
【忘れた理由をしっかり聞く】
人間は「忘れる」能力が備わっているので,忘れないようにする手立てを考えることが必
要です。まずは,なぜ「忘れた」のか原因を把握しましょう。
①は本人の不注意のため,忘れないための手立てを考えなくてはなりません。②,③は家庭
の状況に起因する部分もあるので,家庭と連携を取って対応する必要があります。④は学習意
欲の低下や苦手意識が原因となってい
るため,本人と面談することや,授業
改善を行う必要がありそうです。⑤は
自己管理ができてない場合と誰かにい
たずらされた場合があります。まずは
本人の話を聞いて,後者であれば,い
じめにつながる可能性もあるので早急
に対応する必要があります。⑥も理由
によっては対応が必要です。
体育の授業前,体育帽子を忘れた児童がいた。
普段から忘れ物が多く,授業の直前ということもあり,
厳しく叱責した後,体育を見学させることにした。
状況の把握
担任の指導は適切でしょうか?
・子供たちの忘れ物に場当たり的な指導をしてい
ます。
・なぜ忘れ物をしたのか,理由を聞いていません。
「体育帽子を忘れた」場合の考えられる原因
①持ってくるのを忘れた ②洗濯をしていて持ってこられなかった
③どこに置いてあるのかわからなかった ④体育をしたくないので持ってこなかった
⑤持ってきたが学校でなくなってしまった ⑥友達に貸していた
一言に「忘れ物」と言って
も様々な要因が考えられま
す。本人ではどうしようも
ないこともあるので,なぜ
忘れたのか理由を明らかに
することが大切です。

19
【統一した指導を】
忘れ物をしたときの対応につい
ては,学級・学年で統一し,場当た
り的にならないように注意する必
要があります。例えば…
忘れ物が多い児童生徒
の家庭では,保護者もど
うしていいか困っている
ことが予想されます。
<わざと持ってこない場合>
・忘れた場合,授業を受けさせないなどの対応をしていると起こり得
る事例です。苦手な教科や,やりたくない場合にわざと持ってこな
い(忘れる)ようになる可能性もあります。また,このような対応
は学習機会を奪うことにもなりかねないので注意が必要です。
具体策は?
忘れ物をなくすには,根気強く継続した指導や働きかけが必要です。
様々な取組を行うことも必要ですが,忘れ物がない生活や,忘れ物をゼ
ロにした達成感が,自分たちの成長にどうかかわっていくのかを理解させ
ることや,自分の目指すゴールのイメージを持たせることも大切です。
・朝のうちに忘れた物があれば担任に伝える
・宿題を忘れたときは,休み時間にやる
・友達同士の物の貸し借りは禁止 など
どのように指導していくか学年で話し合ってみ
ましょう。
<本人の不注意の場合>
・連絡帳やメモを活用する。
・何日か前に準備させる。
・チェック表やスタンプカードを活用
して忘れ物をしない意識を高める。
<家庭に起因する場合>
・時間割などを掲示して確
認してもらう。
・電話や連絡帳で準備して
もらいたいものを事前に
伝える。
・家庭の協力が得られない
場合,学校の道具を貸す
などの臨機応変な対応も
考える。(できる範囲で)
保護者との連携
<担任としての意識>
・忘れ物をしないのは当たり前
という意識から,忘れ物をな
くす指導を意図的,計画的に
行うという意識に転換する。
忘れ物に限らず,子供や家
庭に寄り添い,一緒に協力
することで信頼関係を築く
こともできます。

20
事例2 クラス替え当初の集団づくり
生活習慣 集団づくり 問題行動 人間関係 保護者対応 組織的対応 関係機関 その他
小学校低学年 小学校中学年 小学校高学年 中学校
対応の流れ
【まずは今までのルールを確認】
クラス替えのある学年では,複数クラスの全てのルールが揃っていることの方が稀だと考え
ましょう。「違って当たり前」という考え方で取り組んでいくと良いかもしれません。
まずは今までのルールを確認することが大切です。子供たちから直接聞いて把握する方法や,
前の学年の担任の先生方から聞き取る方法もあります。その上で,子供たちと一緒にそれぞれの
ルールの良さを認め合い,子供たちの賛同を得ながら新たなルールをつくっていきましょう。
【クラス替えをしたばかりの頃は特に丁寧に】
担任も子供たちもクラス替えをしたばかりの頃はお互いのことをよくわかっていません。こ
の時期は特に注意深く,丁寧に子供たちを観察していくことが大切です。「前の学年までのこと
を教えてほしい」ということを伝えると,子供たちは喜んでいろいろと教えてくれます。子供た
ちは進級しクラス替えをし,やる気に満ち溢れています。そのエネルギーをどんどん力に変えて
いきましょう。
子供たちは本当に納得していますか?
・一方的にルールを押し付け,厳しい指導をして
います。
・クラス替えをしたばかりで,担任と子供たちの
信頼関係がまだ築かれていないようです。
進級に伴いクラス替えがあった。子供たちは前年度の各々のクラ
スのルールを主張するので,当番活動や席替えの方法などで揉める
ことが多く,人間関係にも悪影響が出始めている。担任はこのまま
ではいけないと思い,一方的にルールをつくり,守れない子供や不
満を言う子供に厳しく指導をするようになった。
状況の把握
問題に直面した場合,同僚の先生に相談することが大切です。ベテランの先
生方はたくさんの方法を知っていますので,教えていただきましょう。
困ったな
ぁ

21
【なぜルールが必要なの?】
状況を把握した後は,いよいよ指導開始です。うまくいかなかったことは,改善していけば良
いのです。中学年や高学年では,「誰のためのルールなのか」「何のためにルールがあるのか」と
いうことを考えさせるのも一つの有効な手段となります。子供たち自身が話し合いの中で考え
たルールは,お互いに気を付けようという意識が高くなります。
【「できたら褒める」がやっぱり大切!】
ルールが決まり日常を過ごしていると,守れていないところに目がいきます。担任としては
叱りたいところですが,できている子供たちを褒めることをより大切にしましょう。
「みんなで決めたルールを守ってえらいね!」「みんなが気持ち良く過ごせるよね!」という
言葉かけをすることで,ルールを守れていない子供たちはハッとします。
【あえて知らせることで勝ち取る信頼】
子供たちが,学級の状態について家庭で不平不満をもらしていたら,クラス替えをしたばかり
ということもあり,保護者も不安になって,担任に不信感を持ち始める可能性があります。今回
の出来事を学級通信の記事にしたり,懇談会で取り上げて説明したりすると,ピンチをチャンス
に変えることもできます。その際には,「こういうことが起きましたが,子供たちと一緒にこの
ように解決することができました」のように伝えると良いでしょう。
児童への指導
話し合いをする時に板書を活用し,視覚的に捉えることができるように
すると,特別な支援を要する児童生徒にもよりわかりやすくなります。
保護者への説明
学級通信や懇談会資料などで取り上げる際には,必ず管理職や学年主任の先
生の確認をとりましょう。
当番活動や席替えの方法に正解はありません。「教師の意図」で
行う場合も多くありますが,高学年になると子供たちが納得して取
り組むことができるか,ということが大切になってきます。この時
期に子供たちとたくさんの話し合いをしてルール作りなどを行っ
ていくことが良い学級経営につながっていきます。

22
事例3 教師が見ていないところで起きた子供同士のトラブル
生活習慣 集団づくり 問題行動 人間関係 保護者対応 組織的対応 関係機関 その他
小学校低学年 小学校中学年 小学校高学年 中学校
対応の流れ
【まずは事実確認をしっかりと】
すぐに時間を確保できないときは「後でゆっくり聞かせて欲しい」ことを子供に伝え,授業を
行っても良いのです。事実確認が不十分なまま指導を行うと,子供が自らの行為を自覚すること
ができず,成長の機会を逃してしまうかもしれません。さらに,一方の話だけに耳を傾けた場合
は,担任に対する不信感が募ってしまいます。
【聞き取りは丁寧に】
「いつ」「どこで」「何をしているとき」「誰に」「どんなことをされた(した)か」などを
一つ一つ質問し,問題となった出来事の前後のやりとりを明らかにします。さらに,そのときの
子供の思いを引き出しましょう。「なぜそうした(された)のか」「どんな気持ちだったのか」
「それをして(されて)どう思ったか」などを問いかけながら,子供に考えさせ,自分自身の行
為や相手の気持ちを見 つめ直すことができるようにしましょう。
休み時間の遊びから戻ってきた2人がもめている。
周りで見ていた子供たちも「A君がたたくのを見た。」
と言うので,担任は「まず,たたいたことを謝ろう
ね。」とA君に促した。「たたいてごめん。」「いいよ。」
という2人のやりとりを見届けてから授業を始めたが,
A君の顔は曇ったまま。
放課後,双方の家庭に今日の出来事を電話で報告した。
状況の把握
本当に事実をつかめていますか?
・担任は,表面上の出来事だけをとらえて,加害児童
に謝ることを促しています。
・子供たちに十分な聞き取りをしていません。
何もしていないのに
たたかれた… ちがう!
あいつがサッカーで反則したか
ら注意したのに,悪口言ってき
て反則やめないんだよ!
叩いたのはうちの子が悪い
けど,反則や悪口のことは
先生知ってるのかしら
聞き取ったことは記録に残しましょう。
先入観を持ったり,誘導的になったりしないようにしましょう。
A君 B君

23
【子供が成長するチャンス!】
聞き取りの中で子供が正直に話したことは,否定せずに聞きましょう。
「悪口を言われてむかついた」「反則をやめないから叩いた」など,マイナスの気持ちや間違
った行為であっても,まずは,子供のありのままの気持ちを受け止めます。そうすることで,「先
生は話を聞いてくれる」という安心感を持ち,子供は冷静に考えられるようになります。
暴力行為は,「相手が傷つくこと」「してはいけないこと」「謝らなければいけないこと」と
して指導する必要がありますが,担任が一方的に教えるのではなく,子供に気付かせるような言
葉を投げかけたり,「どこが間違っていたのか」「どうすれば良かったのか」を一緒に考えたり
するような関わりを意識的に行いましょう。大切なのは,「謝らせること」ではなく,子供が自
らの過ちを認めて謝ることです。もし,自分の過ちに気付き,謝罪の気持ちを持つことができた
ら,それは子供にとって大きな成長です。子供自身の気付きや成長を前向きに認めてあげましょ
う。
【学級全体で共有する】
遊びの中で起きた子供同士のトラブルは,内容によりますが,学級全体に問題提起し,当事者
ではない子供たち一人一人に考えさせることで,集団を育てるチャンスにもなります。
子供に考えさせたいことを明確にし,当事者を悪者扱いせず,誰にでも起こり得る場面として
想像させた上で「こんなときどうしたら良いと思う?」と問いかけ,具体的な言動や解決策を考
えさせましょう。
このような日々の積み重ねが,「友達の過ちに寛容な心」「失敗を前向きに乗り越えようとする
心」を育むことにつながります。すぐに結果が出なくても,焦らず,子供の成長を信じて一人一
人と向き合いましょう。
また,子供たちの仲直りが済んでいる場合は,関係修復に至るまでの気付きや当人同士の好ま
しいやりとりを学級全体に紹介することで,当事者の前向きな気持ちを後押ししたり,折り合い
の付け方をみんなで学んだりすることができます。
【事実を正確に伝える】
学校でのトラブルを保護者に報告するときは,事前に伝える内容を整理しましょう。子
供から聞き取ったメモをもとに「双方の子供の言動」「言い分」「思い」「仲直りに至る
までの過程」「担任としてどのような指導をしたか」「その後の子供たちの様子」などを
具体的に伝えられるようにします。また,問題行動だけが強調されないよう,今回の出来
事を通して見られた子供のよさや成長についても伝えましょう。
保護者の思いに耳を傾け,今後も経過観察することを伝えるなど,少しでも保護者の不
安を拭うことができるよう努めましょう。
子供に気付かせる
保護者との関わり 関係修復後は,経過観察をしっかりと! 子供の行動を観察し,指導の効果や子供の変容を注
意深く見守ります。よい変化が見られたときは,褒め
る・励ますなど,状況に応じた働きかけをしましょう。

24
事例4 グループづくりに関するトラブル
生活習慣 集団づくり 問題行動 人間関係 保護者対応 組織的対応 関係機関 その他
小学校低学年 小学校中学年 小学校高学年 中学校
対応の流れ
【実態把握と種まきを十分に行う】
子供の意思や自主性を尊重するのは大切なことですが,グループづくりを子供たちに任せる
ためには,「子供たちの人間関係の把握」と「事前の働きかけ」が不可欠です。
それらを怠ったまま,自由に決めさせると,表面上は上手く決まったように見えても,心の中
で不満を抱えていたり,その後の人間関係に亀裂が入ったりする場合があります。
宿泊研修のグループづくりを子供たちに任せたところ,
消極的な子が数名いたので,周りを見て自分で動くよう
に声をかけた。幸いにも,「こっちに来ない?」と,誘
いの声がかかり,誰も余ることなく決定した。
ところが,翌日から登校をしぶる子供が出てしまった。
事前の準備
子供に任せる準備をしましたか?
・担任は子供たちの人間関係の把握ができてい
ないまま,グループづくりを任せています。 ・消極的な子供の理由を聞かずに,自主的に動い
てグループをつくるよう声をかけています。
私も一緒にって
約束してたのに 5人ピッタリだね!
・休み時間の過ごし方 ・登下校の様子 ・放課後の遊びの様子
・同好会や部活動での人間関係
・学習中の様子〈例〉自由に交流する場面を設けて様子を見る。
移動教室(図書室等)で自由に座らせて様子を見る。
人間関係の把握
・見えないところでのトラブルを防ぐためにグループの人数などを事前に伝えない。
・口約束は無効であることを伝える。(人数が合わなければ約束は叶わないので無意味)
・その行事のねらいや身に付けさせたい力を伝える。
・決め方を話し合い,教師からの条件を伝える。
〈例〉「自分達で決めたい」→全員が気持ちよく当日を迎えられるように決めること
宿泊班と活動班は,別の人と組むこと
「くじで決めたい」 →結果を見て大げさに喜んだり落ち込んだりしないこと
・自分たちで相談して人数が合わなかった場合の解決方法について話し合う。
〈例〉6人班をつくりたいのに「5人」「7人」に分かれてしまったらどうする?など考え
られる場面を想像しながら,解決策を考えさせる。「人数が多い方から,1人動けば
いい」などの意見が出た場合には,誰もがその1人になる可能性があること,その
時どんな気持ちになるかを考えさせる。
事前の働きかけ

25
【子供たちの動きを見てサポートする】
宿泊行事のグループづくりは子供たちにとって,大きな関心事です。事前の働きかけを行って
いても,いざ決めるとなると,子供たちがどのような反応をし,どのような言動をするかわかり
ません。スムーズに決まることを願っていても,全員の希望が100パーセント叶うことは,ま
ず無いと言ってよいでしょう。どこかで譲り合ったり,折り合いを付けたりしなければならない
のです。
無用なトラブルを避け,少しでも気持ちよくグループづくりをするためには,担任の目の届く
ところで相談させたり,くじを引かせたりすることが重要です。
もし,自分勝手な言動をする子供がいても,目の前で見ていれば「自分が言われたらどう?」
とその場で制することができます。また,周囲への気遣いや心温まるやりとりを見たときにも,
すかさず褒めることができます。
学級の人数が多く目が届きにくい場合は,一度に全員を動かすのではなく,「男子→女子」と
分けて順番に活動させ,その様子を一方が見守るなどの工夫をすることも有効です。
その場合は,スムーズに決まりそうな方から動かし,その様子をもう一方の子供たちに見せ,
好ましいやりとりをさり気なく褒めたり,取り上げたりしましょう。
いずれの方法でも,子供たち一人一人の仕草や表情,つぶやき,動きを教師がよく見て違和感
を感じたら,すぐに「どうしたの?」とサポートできるようにします。
【フォローを忘れずに】
グループづくりの際,周囲のために譲ってくれた子供がいた場合は,無理をしていないか(周
囲から無言の圧力がかかっていないかなど)をよく見極めます。本人が納得の上で快く譲ってく
れたなら,その子の行動に感謝と敬意を示すとともに,その子ばかりが我慢をする立場にならな
いようにフォローしましょう。
〈例〉バス座席では,譲る立場にならないようにフォローする。
【気になる様子は早めに伝える】
グループづくりに関わって気になる様子が見られた場合は,子供に寄り添うとともに,その日の出来事
や子供の様子などを丁寧に保護者へ伝えます。我が子が暗い表情で帰宅すると,保護者も不安になりま
す。帰宅後の子供の様子を聞いたり,保護者の思いを聞いたりする中で,今後の見守り方について相談
し,少しでも不安を拭うことができるよう努めましょう。
子供に寄り添う
単学級でない場合は,学年の先生方で相談して,
グループ決めの日時を合わせましょう。班の人数等
が漏れると,担任の見えない所で約束が生じること
もあり,公平さが失われます。
時間割
……………
……………
保護者との関わり 学級通信
…………
…………
学級通信を有効活用しましょう。担任
の思い,子供の様子など,どのように取
り組んでいるのかを伝えることで,保護
者の理解を得られるよう努めましょう。

26
事例5 学習発表会などの行事における配役決めに関するトラブル
生活習慣 集団づくり 問題行動 人間関係 保護者対応 組織的対応 関係機関 その他
小学校低学年 小学校中学年 小学校高学年 中学校
対応の流れ
【いつ?どのように?準備不足は要注意!】
劇の配役に限らず,学習発表会の器楽合奏の特別楽器や運動会のリレー選手など,子供たちに
とっては,「やってみたい」「なってみたい」と思える場面が,行事の中にはたくさんあります。
全員にやらせてあげたいとは思うのですが,そうはいきません。やはりオーディションで決める
ことが多いようです。その際に,オーディションの日程(欠席者の対応も含む)や方法(台詞や
動き),評価する人など,できる限りの準備をし,事前に知らせておくことも大切です。
また,中学年や高学年では,前の学年の先生方にどのような方法をとっていたのかを聞くこと
も良いでしょう。
【なぜ意欲がもてないの?】
子供たちが練習に真剣に取り組まないようでは,学習発表
会は成功しません。オーディションに落ちてしまった子供た
ちの心の声を聞いてみましょう。落ちてしまったことに対する怠惰な心からなのか,以前にもオ
ーディションに落ちてしまった経験からくる諦めの心からなのか,オーディションに合格した
子への嫉妬心からなのか,別の原因からなのか…全てをひとくくりにせずに,一人一人と向き合
うことが必要です。
学習発表会で劇に取り組むことになった。人気の集中し
た役があり,オーディションをすることにしたが,担任の
事前準備が十分にできていないまま行ったため,保護者か
ら苦情の電話が何件か来てしまった。
また,オーディションに落ちてしまった子供たちは意欲
が低下し,練習に真剣に取り組んでいない様子である。
子供たちは本当に納得していますか?
・オーディションの日程や方法など,担任の準備が
不足していました。
・オーディションに落ちた子供に適切なフォローを
していません。 状況の把握
困ったな
ぁ

27
【子供たちへの期待を伝える】
状況を把握した後は,いよいよ指導開始です。まず,学習発表会をどのような行事にしたいの
かということを学級や学年で話し合います。(本来はオーディションの前から話し合っておくこ
とが望ましい)そして,担任からも,子供たちに「どのような姿を期待しているか」を伝えます。
そうすることで,どのような意識をもって取り組むことが必要で,どのような練習が大切なのか
をみんなで考えます。低学年は低学年,高学年は高学年なりに,自分たちの言葉で伝え合うこと
が重要です。
【オーディションに落ちたらおしまい?】
学習発表会の劇は,一人でも欠けると完成しません。一つの台詞しかない役でも,仲間のため
にその台詞に全力で取り組めるかが大切になってきます。「オーディションに落ちて,なりたか
った役になれなかったらおしまい」という考え方ではなく,オーディションに合格した友達を応
援し,自分に与えられた役を思いっきり演じられる子供たちを育てたいものです。また,高学年
では,オーディションに落ちてしまった子供たちに音響や照明などの仕事を任せて,裏方として
の達成感を味わわせるなどの工夫をすることもできます。
【保護者も納得する説明を!】
今回の場合,子供たちがオーディションについての不満を保護者に伝え,何件かの苦情電話に
つながったと考えられます。これを防ぐためにも,事前にオーディションに関する事柄を周知し
ておく必要があります。また,オーディションに落ちてしまった子供たちの様子が心配な時に
は,家庭に電話を入れることも大切です。「○○君はオーディションに落ちてしまったのですが,
大変よくがんばっていたので,ご家庭でも励ましてあげてください。」という言葉があるだけで,
保護者も子供も学習発表会へ前向きな気持ちになれます。
児童への指導
学年で取り組む時には,子供たちで決めたことなどを掲示物にして目
につくところに貼っておくと意識が高まるようです。
一年間を通して,どの子供たちも輝くことができるよう担任が配慮を
することも必要です。同じ子供たちばかりが行事で目立つことのないよ
うにすることも保護者対応の一つです。
担任にとって学習発表会は,何度もやってくる行事の一つに
すぎませんが,子供たちにとっては大きな舞台で発表するまた
とないチャンスです。教師が思っている以上に,子供たちや保護
者は重要視しているという意識を忘れないことが大切です。

28
生徒Aは行動力の高さで,学級内でも一目置かれる存在感がある生徒である。Aと共に行動するグ
ループでは,Aが強い口調で生徒Bと生徒Cに接したり指示を出したりする姿があったが,特に問題
があるように見えなかった。しかし,Aの言動が自己中心的であるとい
う訴えがBとCから担任にあった。そのため,担任はAを適宜指導した。
B,Cからは関係は良好であるとの返答があり,安心していた。
しかし数日経って,B,CはAにされてきたことと同様の仕返しをし
ていった。Aは遅刻を重ねるようになり,ある日,自宅付近の公園で「B
とCに金銭を要求されたが,家の人に相談しても聞いてもらえない。」
と泣いているAを担任が発見するという事態に陥っていった。
事例6 適切な初期対応で防止が可能ないじめのケース
生活習慣 集団づくり 問題行動 人間関係 保護者対応 組織的対応 関係機関 その他
小学校低学年 小学校中学年 小学校高学年 中学校
対応の流れ
【詳しい状況の聞き取り】
先入観を排して,客観的事実とそれぞれの気持ちを区別して聞き取りを行っていきます。「〜
をした」ということと,「〜な気持ちだったから」というのは別のものです。A,B,C1人
ずつから個別に話を聞いていき,時系列に整理しましょう。
【B,Cへの指導】
生徒BとCの「金銭要求の行為」は完全に法律への抵触行為であり,
「いじめ」と認定されます。初めに担任が中心となって,学校でBとC
には指導を行い,その後,保護者を同席させての学年主任,生徒指導部
長,担任が連携して,会議の場を設け,金銭要求の事実に対しての指導
を行います。
【Aへの指導】 生徒Aには,B,Cへの高圧的態度が起因したことを伝え,なぜ今回このような事態に悪化
してしまったのかを考えさせましょう。B,Cと話をし,今後はどのような関係にしていくの
かを生徒同士の話として納得させ,そのことについては,保護者にも同席してもらって伝えて
いきます。
状況の把握
具体的対応
学級の人間関係を正しく把握していますか?
・日常の様子から人間関係の把握が不十分です。
・児童生徒の聞き取りを丁寧に行っていません。

29
「いじめ」とは,「児童生徒に対して,当該児童生徒が在籍する学
校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係のある他の児
童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネッ
トを通じて行われるものも含む。)であって,当該行為の対象とな
った児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。」とする。なお,起
こった場所は学校の内外を問わない。(H25 文部科学省)
「軽い言葉で相手を傷つけたが,すぐに加害生徒が謝罪し教員の指導によらず
して良好な関係を再び築くことができた場合においては,学校は『いじめ』と
いう言葉を使わずに指導するなど,柔軟な対応による対処も可能である。」と
されています。本事例も,初期対応で心地よい接し方を学ぶような生徒指導を
行い,双方納得できていれば,深刻にならなかった可能性も大きいと言えます。
つまり,いじめの捉え方は…
○1回だけでもいじめ
○被害の程度は関係ない
○加害者側の意図は関係ない
○影響を与え合う関係もある
特に本件
では…。
【基本スタンス】 生徒Aの行動がエスカレートすれば,生
徒Bと生徒Cは「いじめだ」と訴える可能性
があるという感覚を持ちましょう。もし,事
態が悪化して,このような事態に陥ってし
まったら,生徒は嫌な思いをしなくてはな
りません。それを避けて,この事案を生徒同
士の人間関係づくりの機会として利用していくという方針で取
り組んでいきましょう。
【初期段階での情報収集と対応】 担任は,B,Cから訴えがあった時点で,「Aのことをどう思っているのか」と
いう点や「どのように行動を改めさせたいか」ということについて,聞き取りをし
ましょう。また,同じ学年や教科担任の先生方には,生徒達の状況を伝えておき,
その交流の中で得た客観的事実をAに伝えて,どのような状況になりそうかを予測
させしょう。
そして,Aは成長していけば力を発揮する生徒であると信じ,「Aの言動には影響力があり,他者に指
示を出す時には言い方や態度に気を付けてあげるだけで,みんな気持ちよく生活できる」ことを伝え,A
を育てていく視点を持ちましょう。加えて,Aの保護者には,できるだけ生徒本人の気持ちに寄り添うよ
うに協力を求めましょう。
しかし,指導の限界を感じたら…
・懸命な指導に対して,暴力など法律への抵触行為を繰り返す場合 ・繰り返しの指導に対して,改善が見込めない場合 ➡上記の場合には,関係機関(警察,児童相談所等)に協力を求める選択
肢もあります。その際も,任せきりにせず,連携を前提にした指導を行 っていくという役割分担を意識した対応が必要な事態もあります。
知っておきたい
現在のいじめの
定義と解釈
改善策は?
いじめの対応は
組織的な認知からはじめる。
・いじめでないと即断しない。
・問題がすぐに解決しなくとも,生徒と共に悩み
ながら,共に歩むスタンスでいたい。

30
事例7 持ち物に関するトラブル
生活習慣 集団づくり 問題行動 人間関係 保護者対応 組織的対応 関係機関 その他
小学校低学年 小学校中学年 小学校高学年 中学校
対応の流れ
【初期対応を慎重に】 いたずら書きをその場で消しています。
個人の持ち物へのいたずらは,初期対応を焦ると,その後の指導が難しくなる場合がありま
す。被害児童の心のケアを第一に考えて行動したつもりでも,それが裏目に出てしまうかもしれ
ません。憶測が一人歩きしたり,不信感を招いたりすることもあります。
~教室では~ ~家庭では~
【記録と観察をしっかりと】
被害に遭った子供に詳しい状況を聞き,現物を預かりましょう。それができない場合は,コピ
ーや写真をとってから,いたずら書きを消して本人に戻します。また,訴えのあった箇所だけで
なく,他に気になる点がないかを十分確認しましょう。
このようなトラブルでは,様々な可能性があることを考えなければいけません。「意図的に行
われた嫌がらせ」「偶発的に行われた悪ふざけ」「集団によるいじめ」「本人による自作自演の行
為」…など,決して口に出すことはできませんが,子供たち一人一人の表情や様子をよく観察し
た上で,日頃の人間関係,学級の実態などを考慮し,どのように情報収集するかを学年の先生方
と相談しましょう。被害に遭った子供の心に寄り添い,担任が味方であることをしっかりと伝
え,少しでも不安を拭うことができるよう努めます。
中休みの後,教室に戻ってきた子供から,自分の持ち
物にいたずら書きがあるという訴えがあった。
確認すると,心無い言葉が書き込まれていたので,学
級全体に状況を伝え,情報を募った。その場では,何も
分からなかったため,被害に遭った子をなぐさめながら,
いたずら書きを消し,様子を見ることにした。
状況の把握
素早い対応が最善でしょうか?
・担任は,いたずら書きについて知っていること
はないか,すぐに学級全体に情報提供を求めて
います。
・書かれた子供の気持ちを考えて,心無いいたず
ら書きをその場で消しています。
私のノートに「うざい」
って書かれている…。
太郎くんが一人で
教室にいたよね。
私も見た!
あやしくない?
すぐに先生が
消したって…
証拠隠滅?

31
【犯人捜しととらえられないように】
情報収集は,子供の記憶が薄れないよう,その日のうちに行うことが望ましいですが状況によっ
て対応の仕方が異なります。「被害に遭った子供とクラスメイトの人間関係が円滑な場合」「日頃
からトラブルを抱えていた場合」「学級の雰囲気が落ち着かない場合」「子供が特別な支援や配慮
を要する場合」など,それぞれの状況に合わせて,座席が近い子供に聞いたり,学級全体に呼びか
けたり,個別に聞き取りを行ったりします。
ただ,いずれの場合も次の点に留意しましょう。
①被害の内容をどこまで伝えるか《プライバシーへの配慮・情報の限定》
②犯人捜しと思われないような聞き方・話し方《困っているから教えて欲しいという姿勢》
③担任の思い・願いを伝えること《人を傷つける行為は許されないことだが,書いた子がどのよう
な心境で行為に至ったかを心配したり,自ら打ち明けに来てくれたらどれほど嬉しいかを話し
たりする》
【学校は教育の場→ 学びの機会となるように】
【明らかとなっている事実を伝える】
加害児童の保護者に説明する際は,親の不安に寄り添いつつ,事実を明確に伝えます。子供の人格を否
定するような発言や担任の推測による発言は慎みましょう。被害児童の保護者には,上記の点に加えて,
今後の子供の心のケアや再発防止に向けた取り組みについて,具体的にどのようなことを行うかをしっ
かり伝えるようにしましょう。
情報収集
子供の様子や状況などから,加害児童
が明らかになっても,追い詰めないこと
が大切です。矛盾点がある場合は,冷静
に指摘します。どんなことも受け止める
姿勢を保ち,子供が話せる雰囲気づくり
に努めましょう。
加害児童が行為を認めた場合
・行為に至った背景や心情に理解を示しても,
行為自体は正当化できないことを指導する。
・相手の気持ちだけでなく,このような行為に
よって自分自身が周囲の信頼を失うことな
どを考えさせる。
・正直に話した子供の気持ちを受容するととも
に,成長を願う担任の思いを伝える。
・相手への責任の取り方を考えさせる。
加害児童が明らかにならなかった場合
・犯人捜しを行うのではなく,学級全体で人
の持ち物へのいたずらについて考える場
を設ける。(学級指導,道徳との関連)
・人を傷つける行為は絶対に許されないこ
とを毅然とした態度で伝えるとともに,
このようなことが起きないようにするた
めには,どうしたらよいかを学級全体で
考える。
人間関係のもつれなどが背景に
ある場合は,家庭訪問をするか,
来校を依頼し,直接会って説明す
ることが望ましいです。
子供に考えさせる
保護者との関わり

32
事例8 問題行動に対する対応と信頼関係づくり
生活習慣 集団づくり 問題行動 人間関係 保護者対応 組織的対応 関係機関 その他
小学校低学年 小学校中学年 小学校高学年 中学校
対応の流れ
自分の納得いかないことがあると,我慢できずにすぐに手を
出してしまうA君。親も「やられたらやり返せ」という理不尽
な躾をしている。
ある日,A君は「B君に嫌なことを言われた」とB君に手を
あげようとしていたので,担任が間に入り話を聞く。話をした
段階では納得した様子を見せていたが,その日の放課後,A君
はB君を待ち伏せし,殴りかかってしまった。
状況の把握
【問題が起こるまでの背景】
A君は多動傾向・衝動性を持ち合わせていて,小学校の頃から多くのトラブルを起こしてい
ました。さらには,基本的に自分の非を認めようとはしない(「周りが悪い。自分は悪くない。」
と主張する)傾向がありました。また,小学校の頃から保護者と学校の関係もあまり好ましく
ない状況が続いていたようで,中学校でも頻繁にクレームが届いていました。
※親の価値観が大きく影響していると思われる。
問題解決を急いでいませんか?
・聞き取りをした段階で解決したと思っています。
・A君の特性を把握していながら適切な指導を行っていません。
【当該児童生徒の心情の整理を】
聞き取りと指導が混在してしまうと,本当に大事なこと(伝えたいこと)がぼやけてしまい
ます。まずは,児童生徒の心情がどのように変化(A君の場合は「納得いった様子」→「殴っ
てしまった」)したのかを丁寧に聞き取りましょう。
【場所や状況によって児童生徒の姿は「変化」する】
担任の先生の前・友達の前・保護者の前など,児童生徒は場面によって違った姿を見せます。
目の前の姿だけでその児童生徒を理解したつもりでいると,思わぬ落とし穴が待ち受けている
もの。多角的な視点をもって児童生徒を見つめ,より深い児童生徒理解に繋げられるようにし
ましょう。

33
「殴った」という事実がある以上,A君
が反省しなければならないのは当然。し
かし,それだけを押し付けるのは,リス
クが大きいだろうなぁ…
対応につい
て
【「聞くこと」の重要性】
児童生徒がトラブルを繰り返し起こしてしまう要因の一つに,「学校
不信」「教師不信」が挙げられます。例えば本事例は,『特性上言葉より
手が先に出てしまい,結果としてそれを一方的に咎められる。保護者も
「学校はうちの子が言っていることは一切信じてくれない」と決めつ
ける』という状況でした。
では,どうすれば児童生徒との信頼関係を築くことができるのでし
ょう。ケースバイケースではありますが,「丁寧に話を聞くこと」が重
要です。担任の価値観や一般論を押し付けるのではなく,まずは児童生
徒の理解に努める(=丁寧に話を聞く)ことが,学校や担任への不信感
の払拭に繋がります。「行為」だけに焦点を当て過ぎないよう,十分注
意しましょう。
【児童生徒理解と保護者理解】
児童生徒理解と同じくらい重要なのが保護者理解です。児童
生徒との関係がうまくつくれていたとしても,保護者との関係
によっては結果的に全て破綻してしまう可能性もあります。
本事例では,保護者と学校の関係があまりよくない以上,情
報を正確かつ迅速に伝えなければなりません。児童生徒を通し
て保護者に伝わる情報はこちら側の意図しない捉えられ方をす
る可能性があるので,正確に伝えるためにも可能な限り家庭訪
問を行い,直接会って伝えるようにしましょう。
【児童生徒の気持ちを理解する】
「悪いことは悪い」というスタンスはブレないこと。し
かし,だからと言って頭ごなしに指導・注意するのは良く
ありません。児童生徒の特性をしっかり理解し,「寄り添
う」「共感する」姿勢を示すこと大切です。

34
事例9 家庭環境の改善が必要な児童生徒への対応
生活習慣 集団づくり 問題行動 人間関係 保護者対応 組織的対応 関係機関 その他
小学校低学年 小学校中学年 小学校高学年 中学校
対応の流れ
【まずは児童生徒からの聞き取りを…】 ・生活習慣,生活環境についてさりげなく聞いてみましょう。
・何か困っていることはないか聞いてみましょう。
「夜,保護者が家にいない」「朝食が用意されてない」など
【保護者と連絡が取れるかどうか?】 ・電話連絡,家庭訪問などで連絡が取れる場合は,学校での様子を伝えたり,本人から聞き取
った内容をそれとなく探ったりしてみましょう。
・連絡が取れない場合は,前
担任や幼稚園,保育園,小
学校などと連絡を取り,情
報収集をしてみましょう。
【情報収集することで原因が見えてきます。】
本人,保護者,前担任などの情報から,本人の努力で解決できる問題かどうかを探る必要があ
ります。本人だけではどうしようもない問題について,いつまでも「しっかりしろ」と言い続け
てもますます辛くなるだけでしょう。
また,家庭の協力を得られない場合は,学校としてどのような対応を取ることができるか,教
職員で共通理解を図り,学校としての対応を統一しておきましょう。
最近,授業中ボーっとしていることが多い児童A。度々,遅刻してくる
こともあり,本人に注意をし,保護者へ協力を依頼した。しかし,なかな
か改善が見られず,児童Aへの指導を続けてきたが,そのうち,忘れ物も
増え,衣服の汚れも目立つようになってきた。状況が悪化しているので,
さらに保護者へ協力をお願いし,児童Aへしっかりするよう指導してい
る。
状況の把握
家庭の状況を把握していますか?
・状況が変わっても対応が変わっていません。
・学校からの一方的な指導で,児童から聞き取りな
どをしていません。
家庭によって環境は様々なので,保護
者の話を聞くことも大切です。一方的に
学校の様子を伝えて,「何とかしてくだ
さい!」とならないようにしましょう。

35
考えられる対応
家庭環境の改善に対して学校でできる対応には限界があります。
すぐに効果が見られなくても諦
めず続けることが大切です。
【まずはケース会議を】
担任一人で抱え込むことのないよう
に,校内で共通理解を図るためにケース
会議を開きます。ここでは児童生徒の状
況を踏まえて,いつまでに何をするか具
体的なゴールを設定し,役割分担(誰が,
いつ,どんな支援・対応をするか)も明確
にする必要があります。
【本人の自立を促す】
本人の頑張りで何とかなる場合は,でき
るかぎりのサポートをしてあげる必要があ
ります。小学校高学年であれば,家庭科で
「食事」や「洗濯」の学習をした時に家
でも実践できるようにします。生活習
慣が乱れている場合は,時間の使い方
を振り返る場面を設定します。必要に
応じてソーシャルスキルトレーニング
を行ってみるのも良いでしょう。
【不登校のケア】
学校に来なくなる
おそれがある場合,まずは不登校になら
ないように対応することが必要です。例
えば,学校が安心できる場所となるよう
に,場合によっては必要な配慮を行
うことが大切です。学校に来る動機
づけとして,プレッシャーにならな
い程度に,当番や係の役割を与えた
り,イベントを企画したり,させた
りするなど,本人に自己有用感を感
じさせましょう。
【保護者との連絡を切らない】
保護者との連絡が取れている場合,
音信不通にならないように対応してい
くことが必要です。日常の様子を記録
しておき,定期的に様子を伝えるよう
にしましょう。祖父母や親戚が近くに
いる場合は,そちらに連絡が取れるよ
うにしておくと良いでしょう。
【関係機関との連携】
学校だけで対応が難しい場合は,躊躇せず
関係機関と連携して対応しましょう。まずは
教育委員会に連絡を入れ,対応を協議するの
が良いでしょう。家庭の状況に合わせて,必
要な支援を得られそうな機関とのつなぎ役
になってもらい,関係機関の方々も交えて,
改めてケース会議を開くなどの対応が考え
られます。
【困り感を共有する】
場合によっては,保護者にも支
援が必要なことがあります。「ネグ
レクト」の可能性があっても,保
護者や児童生徒にとってそれが当
たり前の生活だとしたら,簡単に
改善することは難しいでしょう。
また,今すぐ児童生徒の生命に関わる事
態と長いスパンで生活改善を図っていく場
合とでは,関係機関の関わり方や保護者へ
の支援の方法も異なります。家庭を孤立化
させず,保護者に寄り添って話を聞くこと
を続けていく必要があります。
保護者への支援

36
事例10 様々な要因が複雑に絡み合っている不登校のケース
生活習慣 集団づくり 問題行動 人間関係 保護者対応 組織的対応 関係機関 その他
小学校低学年 小学校中学年 小学校高学年 中学校
対応の流れ
【不登校とは?】
不登校とは,「何らかの心理的,情緒的,身体的,あるいは社会的な要因・背景により,児童
生徒が登校しない,あるいはしたくてもできない状況にあること」を言います。
不登校は,本人の問題ではなく,学校や家庭を含む様々な要因が複雑に絡み合って起こるもの
として考えられています。
【「学校は楽しい」と言っているのに,どうして欠席するのだろうか】
昼夜逆転 親子関係 貧 困 無気力
病 気 学業不振 非 行 いじめ
小学校低学年のA君の事例である。姉が不登校であり,姉が休む時は,「お姉ちゃんが休むなら
僕も休む」と言い,どちらも欠席してしまうことが多い。A君は,人間関係で悩んでいる様子は見
られず,学校に来た時には何事もなかったかのように過ごしている。友達からも「一緒に遊ぼう」
と誘われたり,自分から誘ったりするなど,良好な関係が築けている。本人に聞いても「学校は楽
しい」と言っている。担任は,無理に登校させることがよいのかを悩んでいる。
状況の把握
原因を決めつけていませんか?
・不登校は様々な要因が絡み合っていることが多い
が,子供や保護者の思いを十分把握せずに,原因
を決めつけている。
情報収集

37
働きかけ
【本人への働きかけ~つながりを絶たない~】 まずは,学校を欠席する理由を深く追及せず,気軽に話し合える雰
囲気づくりに努めることが大切です。
不登校が長期化するにつれて本人の心も変容していくので,本人や
保護者とのつながりを大切にし,変化の様子を見極めながらタイミン
グよく対応していきましょう。
本人の意向を確かめずに他児を迎えに行かせたり,家庭訪問や電話
などで子供の状態を確かめずに登校を促したりすることがないよう,
十分注意しましょう。
【家庭への働きかけ~願いに寄り添う~】
家庭のしつけや養育態度についての批判や非難をしないで,保護
者のつらい思いに寄り添い,共に考える姿勢が大切です。
保護者は「登校させなければならない」という意識を持っていな
がらも,登校させられていない状態に焦りを感じています。その場
合は,すぐに登校につなげようと焦らないことが大事であることを
伝えましょう。保護者の話の中には,不登校の子供への働きかけの
ヒントがたくさん隠れています。話を聞くときには,時間軸を基に
これまでの出来事を整理したり,家族関係を図にしたりしながら整
理していきましょう。そして,どのような姿を目標に行っていくの
か,短期,中期,長期に分けて考えてみましょう。
【学校としての取り組み~一人で抱え込まない~】 不登校の問題は,担任が一人で取り組むべき問題ではありません。校内の協
力なしに担任だけで取り組もうとすると,精神的疲弊や無力感に陥りかねませ
ん。
まずは,個別の指導記録を作成し,計画的・組織的に支援する必要がありま
す。登校した場合,温かい雰囲気のもとで自然に迎え入れられるような学級経
営を心がけるとともに,保健室などへの別室登校など,学校としての体制を整
えていくことが大切です。
不登校が長期にわたる場合にはスクールカウンセラーや,教育委員会などに
相談して適切な対応をしていきましょう。
【関係機関との連携】
巻末資料の相談窓口一覧(P.45),スクールソーシャルワーカー活用事業(P.48)を参照。

38
事例11 スマートフォン・携帯電話に関するトラブル
生活習慣 集団づくり 問題行動 人間関係 保護者対応 組織的対応 関係機関 その他
小学校低学年 小学校中学年 小学校高学年 中学校
対応の流れ
【まずは実態を把握する】
【保護者と情報を共有する】
・家庭の状況を把握しましょう。
参観日の懇談会で保護者Aから,「学級でスマートフォン(以下スマホ)や携帯
電話のトラブルは起きていますか?」と質問を受けた。特に児童生徒に聞き取りを
している訳ではないが今のところトラブルの報告はなかったので,「ありません。」
と回答した。
その後,保護者Aから「うちの子が,みんながスマホを持っているから,自分も
欲しいと言われて困っている。」と相談を受けた。
状況の把握 情報モラル教育を意識していますか?
・持たせる前の約束・指導をしていない。
・トラブル未然防止の手立てを意識していない。
児童生徒の所持率はどのくらい?
釧路市内小学生 約55%
釧路市内中学生 約79%
家庭でルールを決めている?
・「約束事なし」と回答した中学生は約35%
・「約束事なし」と解答した保護者は約12%
保護者と子供の認識のズレが見られます。
スマートフォン・携帯電話などの利用に関するアンケート
(平成30年度実施より)
どんなルールを
決めていますか?
なぜ持たせていますか?
・使う時間
・使う場所
・使う目的 など
持つことによるメリット・デメリットを共有
○所在がわかって安心
○すぐに連絡が取れる
●事件に巻き込まれる可能性
●知らない人とも簡単に連絡が取れる
家庭も学校も情報モラルの意識を高めましょう。

39
安心ネットづくり促進協議会(https://www.good-net.jp/)
のホームページを活用してみましょう。
・出前講座,研修会の紹介~携帯電話事業者やSNS運営会社の出前講座の案内など
・青少年のスマホ利用のリスクと対策~フィルタリングやセキュリティに関する情報など
・青少年の安心安全なインターネット利用のために~小,中,高,保護者向けの啓発資料など
・他にも様々なコンテンツが用意されています。
具体的な取組
児童生徒,教員,保護者と対象に合わせた講座があり
ます。スマホ・携帯電話の利用上のルールやマナーから
実際に起こったトラブルをもとに未然に防ぐ方法やリス
ク回避のスキルなどを紹介してくれます。
携帯電話事業者による出前講座を実施
近年,釧路市内の小中学校でも携帯電話事業者によ
る出前講座の実施が増えています。
スマホ依存への対応
近年,社会的問題にもなってい
るスマホ依存の要因は様々です。
「熱中しすぎて止められない」「使えない
とイライラする」「使用している時間がどん
どん増えている」「不安やストレスを紛らわ
すために使っている」等,児童生徒の実態に
合わせて対応することが必要です。
使用状況を把握する
各学校で実施している「生活リズ
ムチェックシート」にスマホの利用
時間の記入欄を設けて,実態把握や
目安の時間を周知する。
SNSのトラブル
SNS上で起きているトラブルは情報が
少なく,早期発見は困難です。
定期的にネットパトロールを行うととも
に,児童生徒の何気ない会話などから情報
が得られないか普段から意識することも必
要です。
学校生活に支障をきたすようなトラブル
に備えて,家庭と連携を図りながら,組織的
に対応できる体制を整えておくことも必要
です。
スマホ・携帯電話と上手に付き合う方法を家庭と学校で共有しましょう。

40
事例12 組織としての対応
生活習慣 集団づくり 問題行動 人間関係 保護者対応 組織的対応 関係機関 その他
小学校低学年 小学校中学年 小学校高学年 中学校
対応の流れ
【該当児童生徒・保護者との対話】
まず行うべきは,該当児童生徒および
保護者からの情報収集と状況の把握です。
【学年・生徒指導部・学校での協議】
問題が担任で留めておけない状況の場合※1には,学年団で共有したり,生徒指導部へ報告し
たりして,対応を協議する必要があります。緊急時には,学級・学年・教科担任で連携をとり,
さらに担任外の教職員にも協力を求め,迅速に対応することが大切です。各学校における組織
対応については,「生徒指導マニュアル」等を今一度,確認しましょう。(P.41「組織対応の
関係図」参照)
【連携の視点】
それぞれの事案で状況が
違うため,一概にまとめら
れませんが,組織連携の視
点としては,指導の範囲(関
係者の人数と関係性など)
や緊急性,指導の複雑さ(原
因が家庭環境にある場合な
ど),継続性(継続的な指
導・観察が必要か)などが
挙げられます。
生徒指導は「担任が抱え込まないことが大切」と言いますが,校内でどのように連携を
図っていくとよいのでしょうか。
状況の把握
「みんなで児童生徒を育てる」
という視点が大切です。
・児童生徒にとって,本音を語りやすい状況を考
えましょう(対応する教員,場,時間等)。
・組織対応の目的は,迅速に,多面的に児童生徒
と向き合っていきましょう。
※1問題を担任に留めておけない状況の場合の例 ・他学級,他学年,他校等に関わる場合 ・諸費未納等の金銭的な事柄 ・児童生徒,保護者と担任とのコミュニケーション不全 ・未解決な状況が長期にわたる場合 など
なし あり (緊急性)
広い
狭い
(指導の範囲)
連携の必要性
大
なし あり (継続性)
高い
低い
(指導の複雑さ)
連携の必要性
大
□ 指導の複雑さ × 継続性 □ 指導の範囲 × 緊急性

41
【多様なサポート体制を】 ■継続的な指導・対応が必要な場合は,担任とその他教職員との間で,場所や時間,取組のねらい等を
共有し,実際の対応をお願いすることも必要になることがあります。この場合,担任は担当の教職員
と連絡を密に取り,任せきりにならないように注意しましょう。
■担任としてどう対応してよいか,またはどこまで他の教職員にお願いしてよいかわからないことも多
いのが実際です。困った場合には,学年団をはじめ,管理職や生徒指導部長,養護教諭,特別支援コ
ーディネーター等に相談しましょう。
■該当児童生徒・保護者が担任以外の教員と話す機会も大切な場合があります。必要に応じて場を設定
し,多面的な情報収集に努めましょう。
■問題を校内に留めておけない状況の場合には,関係機関への相談を協議する必要があります。
(P.42「関係機関との連携」参照)
【連携のポイント】 担任から連携を広げるときに重要なのが『情報』です。客観的な事実やその背景,経緯等を共有する
ことで,先の展望をもつことができます。「情報を集め記録すること」,それらの「情報を正しく伝える
こと」に焦点をしぼり,以下にそのポイントを記します。
学級担任
学年団 (学年主任・学年指導部)
全職員
学校長・教頭
生徒指導部 (部長・学校カウンセラー)
該当児童生徒
保護者
教育委員会教育支援課
学 校 家 庭
関係機関
この関係図は,一例です。 勤務校の生徒指導マニュアル等でもご確認ください。 参照 P.45
「相談窓口一覧」
▲ 組織対応の関係図
特別委員会 (生徒指導委員会等)
レベル1 学級担任で指導・対応する範囲 □対応に時間が比較的かからない
事案
レベル2 学年内で,学年主任・学年指導部を
中心に指導・対応する範囲 □複数の教員で対応するのが望ましい事案
レベル3 全職員に周知し,生徒指導部を中心
に指導・対応する範囲 □緊急性や指導の範囲等から,全職員で対応するのが望ましい事案
レベル4 全職員に協力を求め,関係機関と連
携して指導・対応する範囲 □長期性・継続性等も含め,関係機関と連携して対応するのが望ま
しい事案
□ 報告書(指導カルテ)を作成する
(1)目的
事実・経緯の共有
(2)記載事項
①日時 ②場所 ③関係者についての情報 ④背景・
経緯 ⑤事後指導・経過・配慮事項・申し送り事項など
(3)留意点
連携して対応するには,端的に必要な情報を伝える
ことが大切になります。そのための手段の一つが報告
書の作成です。この際,誰が読んでも正しく伝わるよ
う表現にも留意しましょう。
□ メモを取る
(1)目的
事実の記録,時系列や経緯の整理
(2)記録事項
①日時 ②場所 ③関係者につい
ての情報 ④概要 など
(3)留意点
正確な情報は,事実確認をしたり
時系列を整理したりするのに非常に
重要です。記憶を過信せず,記録を
残すようにしましょう。

42
事例13 関係機関との連携
生活習慣 集団づくり 問題行動 人間関係 保護者対応 組織的対応 関係機関 その他
小学校低学年 小学校中学年 小学校高学年 中学校
対応の流れ
【該当児童生徒・保護者との対話】
まず行うべきは,該当児童生徒および
保護者からの情報収集と状況の把握です。
【学年・生徒指導部・学校での協議】
問題を担任で留めておけない状況の場合(P.40「組織としての対応」参照)には,学年団
で共有し,生徒指導部へ報告し,対応を協議する必要があります。場合によっては,養護教諭
や特別支援コーディネーターにも相談し,アドバイスをもらいます。各学校における組織対応
については,「生徒指導マニュアル」等を今一度,確認しましょう。
また,該当児童生徒・保護者が担任以外の教員と話す機会も大切な場合があります。必要に
応じて場を設定し,より詳しく多角的な情報収集に努めましょう。
【関係機関へ相談する(学校も,保護者も)】
問題を校内に留めておけない状況の場合※1には,関係機関への相談を協議する必要がありま
す。釧路市では教育委員会(教育支援課)が情報を集約し,スクールカウンセラーやスクール
ソーシャルワーカーや不登校学級(さわやか学級・青空学級)等への連携をサポートしていま
す。管理職を通して,教育委員会に相談し,該当児童生徒についての情報共有を図りましょう。
また,該当児童生徒や保護者が,関係機関と話す機会も大切です。学校とはちがう視点で客
観的な意見を聞く場として,保護者に教育委員会を紹介し,相談することを勧めるという手立
てもあります。保護者が関係機関に相談した場合,多くは学校へ報告をもらえますので,そこ
から関係機関と連携することもできます。
生徒指導は「関係機関と連携した対応していくことが大切」と言いますが,具体的には
どのように手続をとったり,連携したりするとよいのでしょうか。
状況の把握
「みんなで児童生徒を育てる」
という視点が大切です。
・関係機関への連絡・相談は,基本的に管理職を
通して行いましょう。
・連携の目的は,関係機関と共に児童生徒と向き
合っていくことです。(手放すわけではない)
※1問題を校内に留めておけない状況の場合の例 ・長期的な不登校 ・家庭内暴力 ・改善がみられないいじめ ・保護者の養育力 ・虐待(ネグレクト等) ・貧困 ・児童生徒,保護者と学校とのコミュニケーション不全 など

43
【連携後こそ大切に】 関係機関との連携の目的は,専門的な視点から多面的に児童生徒について考えていくためです。
ここで大切になってくるのが,関係機関とのゴールの共有です。しかし,ゴールは状況に応じて多様
化するのが実際です。不登校を例にとると,学校の最大の目標は,確かに「在籍校に通常登校できるよ
うになること」ですが,それが容易でない場合が多くあります。したがって,児童生徒の様子を見て,
スモールステップでゴールを設定していくことが必要となります。そして,そこに向けて働きかけ,励
まし,関わり続けることが何より大切です。
最後まで“信頼できる大人”として,児童生徒との関わりを保ち,できる限りの働きかけを継続して
いくことを大切にしていきたいところです。
担任
学年団
養護教諭
管理職
生徒指導部
該当児童生徒
保護者
教育委員会教育支援課 (MOO)
教育研究センター (千歳町)
さわやか学級(城山小) 青空学級(北中・城山小)
スクールカウンセラー
スクールソーシャルワーカー
こども家庭支援センター(旭町)
学 校 家 庭
該当児童生徒・保護者との
充分な対話
担任以外の教員と話す機会をもつ
学校以外の機関と話す機会をもつ
該当児童生徒・保護者
についての情報共有
関係機関
への相談
・連携
関係機関
地 域
民生委員 町内会
この関係図は,ほんの一例です。 状況に合わせて,連携を考えていくことが大切です。
参照 P.45
「相談窓口一覧」
市立病院
▲学校・家庭・関係機関の関係図
【例】
さわやか学級 行事への参加〔もちつき交流会・終業式など〕
定期的な面談
・ 原籍校の配布物を渡す
・ 学習・生活の様子を聞く
・ 一緒に給食を食べる(原籍校にて)
全日程参加できなくても,少しでも顔
を出して,様子を見る,顔を合わせる,
話すことを大切にしたいですね。
面談の場所は,さわやか教室・原籍校・
児童生徒宅のいずれでも構いません。児
童生徒との面談がかなわなくても,保護
者とのつながりを維持することも大切で
す。
特別な面談
・ 行事等への参加について一緒に考える
・ 新しい一歩を一緒に考える
・ 進路・将来について一緒に考える
児童相談所(桜ヶ丘)
可能であれば,機会をみて,じっくり
話したいところです。担任としての思い
を伝えることを大切にしたいですね。
▶不登校学級「さわ
やか学級」を例にし
た,担任の継続した
働きかけ・関わりに
ついての一例

44
「おかしいな」「どうしたんだろう?」「嫌な感じがする…」その勘を大切にしましょう。
どのような対応が最善なのかは,状況や子供の実態によって異なりますが,小さな違和感を一つ一つ指
導するか,見過ごすかによって,集団の雰囲気は大きく変わります。
また同様に,子供の小さな真心や努力を見つけて取り上げるか,見過ごすかによっても,集団の雰囲気
は大きく変わるのです。
≪一方だけに声援が…≫
コラム ~集団づくり~
日常生活の中で「あれっ?」と思う瞬間はありませんか
≪嫌な感じのゴミが…≫ ≪ぴったり付けていた
机にすきまが…≫
≪発表中の周りの雰囲気が…≫ ≪トイレの中から
複数の笑い声が…≫
◇タイミングを逃さず,その場で毅然と注意する。 ◇さり気なく声をかけ正す。
◇学級全体に問いかけたり,考えさせたりする。 ◇後で個別に呼んで話を聞く。
◇様子を見守りながら情報収集する。 ◇教師の思いを伝える。 など
マジうける!
あっはははは
うわっ!
あいつが?
行けイチロー!
いいぞ
イチロー!
イチロー!
がんばって 死
ねえねえ
クスクス
「一緒に行こう!」 「ありがとう」 「持つよ」 「どうやるの?」 「教えようか?」
優しいね
友達思いだね ありがとう
頑張っているね
教えるのが上手いね

45
相談窓口一覧
□教育に関すること
一般教育相談 どなたからでも教育全般に関する相談 教育支援課教育支援担当 23-5189
教育研究センター 42-3311
釧路教育局教育相談電話 43-1475
一般教育相談・メール相談 学校に対する悩み,教育全般,家庭生活に関する相談 教育研究センター 42-3311
相談電話・メール相談 いじめ・不登校などの学校教育に関する悩みについて
子ども相談支援センター 0120-3882-56
北海道立教育研究所
□いじめや不登校について
24 時間いじめカットライン 学校などでのいじめに関する相談に応じ,支援 教育支援課教育支援担当 0120-783-228
教育相談電話・メール相談 いじめや不登校等に悩んでいる子供や保護者の相談 教育研究センター 42-3311
少年相談 110 番 少年非行・いじめ・犯罪被害・悩み等の相談 北海道警察本部少年サポートセンター
0120-677-110 011-242-9000
子どもの人権 110 番 いじめ・体罰など子供の人権に関する相談 釧路地方法務局 0120-007-110
青少年相談室 非行・不良行為・家庭でのしつけなどの相談 釧路少年鑑別所 41-5877
不登校相談 不登校が長引いている場合やひきこもりがちな場合の相談 釧路児童相談所 92-3717
家庭相談・メール相談 友人関係やいじめ,不登校で悩んでいる子供や家庭の相談 釧路こども家庭支援センター 32-1150
相談電話・メール相談 不登校や自分の生き方を探している人の居場所,精神的に問題を抱える子供たちの相談 スクールさぽーとネットワーク 32-4080
□子育て・その他について
くしろ家庭児童相談室 児童虐待を見たり聞いたりした時の連絡 こども保健部こども支援課 31-4204
0120-783-946
育児・健康相談 家庭が抱えている様々な問題に関する相談 こども保健部健康推進課 31-4525
思春期相談ダイヤル 子供の発育,発達,しつけ,育児,健康相談
子育て相談 思春期における心や体の相談
釧路市中部子育て支援拠点センター 38-5037
釧路市東部子育て支援拠点センター 65-9912
釧路市西部子育て支援拠点センター 65-6112
釧路はるとり保育園子育て支援センター 47-3277
釧路風の子認定こども園子育て支援センター 65-5956
親子つどいの広場「昭和」 55-2231
児童相談 子育ての悩みについての相談 釧路児童相談所 92-3717
心身の発達に関する相談
(就学前)
発達相談・早期療育・児童発達支援
保育所等訪問支援・障害児相談支援
児童発達支援センター(地域支援相談室) 44-3555
44-1033
障がい児の通園施設(児童発達支援) 児童発達支援センター(野のはな園) 44-1022
障がい相談 障がいをもつ方や障がいの疑いのある方が地域で生活するための相談 釧路市障がい者基幹相談支援センター 38-1181
ひきこもり相談 ひきこもり等についての相談
北海道釧路保健所 65-5825
釧路こども家庭支援センター 32-1150
釧路児童相談所 92-3717
DV相談 配偶者や恋人からの暴力についての相談
配偶者暴力相談支援センター 41-1110
こども保健部こども支援課 31-4204
駆け込みシェルター釧路 32-7704
人権相談 人権問題や様々な問題 法務局人権擁護課 0570-003-110
子どもの人権 110 番 0120-007-110
消費生活相談 訪問販売,物品購入の問題 消費生活センター消費生活相談室 24-3000

46
さわやか学級・青空学級
1 設置目的
・様々な要因により学校生活に適応できない児童生徒に対し,集団生活への適応を促し,学校生活への復帰を支援するため,
平成6年4月に設置。
2 設置場所
・さわやか学級(小学校) 釧路市立城山小学校(釧路市城山 1丁目 14番 35号)
・青 空 学 級(中学校) 釧路市立北中学校分教室として釧路市立城山小学校に設置
さわやか学級・青空学級職員室 ℡:(0154)42-4222 E-mail:[email protected]
3 入級対象児童生徒
・釧路市の小中学校に在籍し,心理的,情緒的,あるいは社会的要因により不登校になっている児童生徒
4 対象児童生徒の入退級の決定
・教育支援委員会(不登校専門部会)が入退級の判定を行い,釧路市教育委員会において決定・通知を行う。
5 指導の方針
・教師と児童生徒の心の通った人間関係の育成と家族の調和的な関係を調査し,不安や緊張を取り除き情緒の安定を目指す。
・体験的活動を取り入れ,自信が持てるような経験を通して,積極的に自己実現に向かう意欲を育む。
・社会性の未熟さ,幼稚さの克服を支援し,年齢相当の発達を促す。
・集団に適応し,何事にも意欲的に立ち向かう態度を養う。
・個々の児童生徒の実態に応じた学習内容を取り入れ,基礎学力の向上を図る。
・通常の学級と交流を図り,地域の学校復帰を促す。
・教育支援委員会及び不登校専門部会との連携のもと,諸関係機関と協力し,効果的な指導を行う。
6 指導内容・方法
児童生徒の状態や発達に応じた学習を行い,家庭訪問指導,学級での指導(個別指導,集団指導)を通し,地域の学校への復
帰を促す。また,保護者に対しての教育相談を通し,対象児童生徒を取り巻く家族関係のあるべき姿をともに求めていく。
(1) 学級の指導
児童生徒自身が学習内容や時間を決めたり,選択したりすることから,徐々に通常の学校の時間帯に沿って学習し,他の児
童生徒,教師とのかかわりの中で自己実現や集団内で適応できるように援助する。
・生徒指導~孤立感,不安感,緊張を和らげ,情緒の安定,解放を図り健全な生活ができるよう援助・指導を行う。
・教科指導~児童生徒の個性,能力,学力,興味,関心などに配慮した学習内容とし,効果的な指導を行う。
・学級行事~自主的な判断力や協調性,役割分担などの社会性を養うため,体験教室や炊事遠足,宿泊研修等の集団活動の行
事を行う。
(2) 訪問指導
・受容的な対応を基本とし,個々の児童生徒との信頼関係の確立を図る中で,児童生徒自身が心理的なつまずきを洞察し,且
つ自己を見つめ直し,再登校に向かうための援助を行う。
・個々の児童生徒の興味,関心を中心に経験領域の拡大や家族相互の望ましいかかわり方について支援する。
(3) 教育相談
・電話,面接相談を行い,児童生徒の抱えている不安や悩みを受けとめ,適切な相談・指導に務める。
不登校相談
入 級 希 望 相 談 受 付
相 談 受 付 面 接
面 接 仮通級開始
仮通級開始 ケース会議
ケース会議 面 接 検 査
面 接 検 査
不登校学級(さわやか学級・青空学級)
入級までの流れ
保護者・児童生徒
保護者・児童生徒
教育委員会(教育支援課)
教育委員会(教育支援課)
教育委員会(教育支援課)
教育委員会(教育支援課)
不登校学級への仮通級(学籍異動なし)
不登校学級への仮通級(学籍は移さない) 教育委員会(教育支援課),不登校学級担当者等による会議
教育委員会(教育支援課),不登校学級担当者等による会議 在籍校からの意見(調査書)
在籍校からの意見(調査書)
面接検査・心理検査
面接検査・心理検査
・・・・・・・・・
・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・
・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・
・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・
・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・
・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・
・・・・・・・・・ 教育支援委員会
就学指導委員会 入級の決定
入級の通知
入級の通知
在籍校
在籍校 不登校学級見学
不登校学級見学
・・・・・・・・・
・・・・・・・・・
教育支援委員会(不登校専門部会)への諮問・答申
就学指導委員会(不登校専門部会)への諮問・答申 教育委員会(学籍を城山小,北中に異動)※在籍校は原籍校となる
教育委員会(学籍を城山小,北中に異動)※在籍校は原籍校となる
・・・・・・・・・
・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・
・・・・・・・・・
教育委員会(学校教育課)
教育委員会(学校教育課)
保護者・原籍校
保護者・原籍校

47
釧路市ふれあい教室
1 設置目的
・様々な要因により学校不適応となった児童生徒に対し,学習指導など個別の指導を行い,集団生活への適応を促すた
め,平成3年5月に設置。
・釧路市教育委員会における教育相談事業の一環として,教育相談
教科指導,生活指導,集団生活への適応指導等を組織的,計画的
に進め,各学校に対する補助的な機能を果たす。
2 設置場所
・釧路市千歳町3-16(釧路教育研究センター内)
℡:(0154) 42-3311 E-mail:[email protected]
3 適応指導教室の名称
・釧路市学校適応指導教室とし,通称「釧路市ふれあい教室」と
する。
4 教育相談,教育活動内容
・児童生徒及び保護者,学校教育関係者等を対象として,主として不登校,学校不適応児童生徒に関する事項について,自
発的な相談(来訪,電話)や訪問,呼び出しによる相談を行う。
・教室では,教科等の学習指導(補充指導)や日常的な生活の指導(個人指導),集団生活への適応指導等を個人の状況に
あわせて行う。指導は基本的にふれあい教室内で行い,社会教育関連施設等での活動も行う。
5 開設期間及び時間
・開設期間は4月から翌年3月までとし,毎年継続する。
・月曜日~金曜日までの午前9時から午後4時まで。
ただし,祝日,年末年始を除く。
6 通室対象児童生徒
・釧路市の小中学校に在籍し,学校生活への適応が困難な児童生徒
・本人が希望し,保護者から申し出のあった児童生徒
・学校その他から必要と認められた児童生徒
7 通室の手続き
・原則として本人が希望し,保護者の同意のあることを学校が認めた場合とする。
・教育委員会は,不登校や適応指導に係る相談があったとき,別に定める手続きにより通室適否を協議し決定する。
・教育委員会は,通室を認めた児童生徒について保護者及び在籍校の校長に連絡する。
・在籍校への復帰についても同様とする。
8 授業日数との関係
・ふれあい教室への出席状況及び指導内容等を記録し,学校(在籍校)へ送付する。
・ふれあい教室の記録に基づき,出席した日は出席扱いとする。
9 通室にかかわる配慮事項
・通室方法は保護者が判断し,交通等の安全に十分配慮させる。
・昼食は弁当など各家庭で準備する。
・学用品や教材(個人用)は各自(家庭)で用意させる。
・児童生徒の健康管理・安全については十分に配慮するが,事故等の場合は在籍校が対処する。
釧路教育研究センター内に設置
されています。
【教室内の様子】
不登校相談
相 談 受 付
面 接
通室の検討
通室の決定
通室の通知
釧路市ふれあい教室
通室までの流れ
保護者・児童生徒
教育委員会(教育支援課)
教育委員会(教育支援課)
在籍校・ふれあい教室・教育委員会(教育支援課)
教育委員会(教育支援課)
教育委員会(教育支援課) 保護者・在籍校
・・・・・・・・・
・・・・・・・・・
・・・・・・・・・
・・・・・・・・・
・・・・・・・・・
・・・・・・・・・
釧路市消防団第3分団
在籍校
ふれあい教室見学

48
スクールソーシャルワーカー(SSW)活用事業 1 地域の課題
釧路市は,全国・全道平均に比べ離婚率,生活保護受給率が高く,ひとり親の家庭や経済的に援助を必要とする世帯の多い
地域である。
不登校児童生徒の中には,さまざまな要因が複雑に絡み合い,長期の不登校状態に陥っている者もいる。また,保護者の養
育能力の欠如など家庭環境に課題を抱え,学校単独では有効な支援展開を行うことができない者も少なくない状況である。
これらの問題解決にあたっては,教育分野からの支援に加えて,保護者や家庭を巻き込んだ地域,福祉機関等を含めた幅広
い福祉的な支援が求められている。
2 事業のねらい
上記のとおり,複雑な問題が絡み合った状況にあり,学校単独では対応が困難な不登校児童生徒に必要な支援を行うため,
スクールソーシャルワーカーを中核とした関係機関が一体となり支援にあたるサポート体制により「教育相談体制の充実」を
図るものである。
また,スクールソーシャルワーカーの活用により,教育分野に福祉の仕組み(「教える」+「支える」という考え)を導入
し,児童生徒が置かれている様々な環境に対する効果的な働きかけを行う。
3 スクールソーシャルワーカー(SSW)の活動
学校と家庭・地域のさらなるつながりのため,また,児童生徒が安心して学校や家庭生活を過ごせるよう,教育と福祉の連
携を行う。悩みや問題を抱えるケースに対して,下記を例とした関わりを行っている。
(1) 各学校の悩みや問題を抱えた児童生徒の状況を把握
㋐不登校実態調査 ㋑SSWの学校訪問 ㋒学校からの連絡(随時)等
(2) SSWは関係機関等と連絡をとり,児童生徒を取り巻く環境等を確認
(3) 各学校等が開催する,校内の「ケース会議」等にSSWを派遣する。また,SSWは解決のための情報収集や
関係機関へのケース会議参加を呼びかける。
4 相談窓口
釧路市教育委員会スクールソーシャルワークアドバイザー 小林 久美
釧路市教育委員会スクールソーシャルワーカー 信行 亜希子
●事業の推進体制
ファミリー サポーター
スクール ソーシャル ワーカー
適応指導教室 指導員
不登校学級 担任教諭
スクール カウンセラー
学校
保護者を含めた家庭
不適応 児童生徒
不登校 児童生徒
地域社会資源 フリースクール などの民間 福祉機関や民生委員 町内会など
各福祉機関 市役所福祉部局 児童相談所など
登校支援
カウンセリング 訪問支援
教室運営 学級運営
連絡調整
相談援助
幅広い支援展開 手厚い支援展開

【 お わ り に 】
本研究専門委員会では,2カ年にわたって児童生徒理解を基盤とした生徒指導の在り方についての調
査・研究を進めてきました。「生徒指導」と一言に言ってもその中身は多岐にわたり,教育現場において
は様々な場面で必要となる教育活動です。その在り方を改めて考察し,「先生方に活用してもらえるもの
を発信しよう」という思いで活動してきました。
今回の研究における柱は,「初任段階教員の実態把握」「生徒指導ハンドブックの作成」の2本でした。
「初任段階教員の実態把握」については現場の先生方の生の声を拾うべくアンケート調査を実施し,そ
の集計と考察を行うことで釧路の若手の先生方の生徒指導への思いや悩み,願いなどを把握することが
できるものとなりました。例え経験年数や立場が違ったとしても大変興味深い結果となっているはずで
す。
また,本ハンドブックは多くの情報収集を行いながら時間をかけて作成しました。学校現場で起こりが
ちな様々な生徒指導上の事例を,「教師の働きかけ」「家庭との連携」「組織的対応」等といった多角的な
視点でまとめております。今回挙げた事例はほんの一部のものでしかありませんが,生徒指導上,役に立
つ「エキス」が盛り込まれております。ぜひご活用いただけたらと思います。
最後になりますが,本ハンドブックの作成にあたり,ご指導ご助言ご協力をいただきました各関係機
関,先生方にこの紙面をかりて感謝申し上げます。
本当にありがとうございました。
(生徒指導研究専門委員会 副委員長 熊谷 亮太)
生徒指導研究専門委員会
委 員 長 春名 健司(釧路市立光陽小学校)
副 委 員 長 熊谷 亮太(釧路市立北中学校)
委 員 山野 哲子(釧路市立鳥取小学校)
小阪 志保(釧路市立鶴野小学校)
常陸 勇馬(釧路市立大楽毛小学校)
竹岡 良太(釧路市立鳥取西中学校)
担当研究所員 渡辺 悟之(釧路市立釧路小学校)

【引用・参考文献】
文部科学省 小学校学習指導要領
文部科学省 中学校学習指導要領
文部科学省 生徒指導提要
文部科学省 国立教育政策研究所 生徒指導リーフ Leaf.1~22
釧路教育研究センター研究紀要第183号 新・学級経営ハンドブック
釧路教育研究センター研究紀要第186号 幼・保・小・中の円滑な連携・接続に向けて
仙台市教育委員会 教師のための生徒指導ハンドブック
茨城県教育委員会 信頼される学校づくりをめざして-保護者と適切なかかわりのために-
栃木県総合研究センター 児童生徒への適切な指導のヒント 事例集
高知県教育委員会 生徒指導ハンドブック~豊かな心を育むために~
第190号 研究紀要
生徒指導ハンドブック
編集・発行 釧路教育研究センター
釧路市教育委員会 教育支援課
〒085-0016 釧路市錦町 2丁目 4番地
℡(0154)23-5189



![1 < $ Ê Ê - 8 Êservicios.educarm.es › ... › 10 › secciones › 47 › contenidos › 619 › disl… · Ê Ê >À} Ê`iÊ ÕiÃÌÀ>ÊiÝ« à V ]ÊÕÌ â>Ài](https://static.fdocumento.com/doc/165x107/5f185ef6844bd46c19055d70/1-8-a-a-10-a-secciones-a-47-a-contenidos-a-619.jpg)