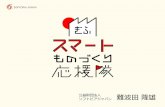Day2-P3-1200 Amazon WorkSpaces による クライアントコン … · お客様の声:なぜ今クラウド型 仮想デスクトップなのか お客様が抱えている 課題
第3章 政策課題とその対応 - Ichihara · 2014-01-24 ·...
Transcript of 第3章 政策課題とその対応 - Ichihara · 2014-01-24 ·...

第3章 政策課題とその対応
Toshiaki Matsuda

38
【図】政策課題の概念図
� 都市の魅力を引き出し、「ともに輝く
元気なふるさと 」をめざすために
は、今からその種を植え付け、10年、20年先のま
ちづくりの芽生えを意識する必要があります。
� そこで、市民生活に関連する多くの問題の
うち、早期に解決しなければならない次の事項
を政策課題として捉え、基本構想に掲げた「ま
ちづくりの戦略」を手法に取り組んでいきます。
*地域で支えあう福祉施策の推進
*子育て支援と責任ある教育の推進
*環境にやさしい持続的発展可能な社会の構築
*市民が安全・安心して暮らせるまちの実現
*地域経済の活性化
*行財政改革の推進
*市民によるまちづくりの推進
情 報
共有化の
推 進
パートナ
ーシップ
の 確 立
政策評価へ の市民参画の 推 進
3つのまちづくりの戦略
いちはら
*
政策課題とその対応
てこ入れてこ入れ
まちづくりの基本的方向
【解決のための施策展開】7つの政策課題

39
◆「まちづくりの戦略」について
【市原市基本構想より】
『まちづくりの戦略とは…』
まちづくりは、単一の主体や限られた地域だけで行えるものとは限りませ
ん。時にはさまざまな主体が連携して進めることもあります。このため、各
主体が容易に情報を収集でき、そして発信できるシステムを整え、情報ネッ
トワークの形成のもと、それを共有できる環境整備を図ります。
また、この前提として、行政の情報公開を一層積極的に進めます。
情報共有化の推進
市民の力や地域の力をまちづくりに活かしていくためには、市民と行政が
それぞれ対等関係の中で持てる力に見合う役割と責任を認識して、協働して
取り組んでいくことが大切です。このため、市民と行政が力を合わせて協働
のためのルールづくりを進めます。
また、相互の連携を円滑にするため、中間支援組織など、新しい仕組みづ
くりをめざします。
パートナーシップの確立
本市がめざそうとする基本的な政策の方向を明らかにし、その実現方向や
現在の水準を示すため、ベンチマーク(「水準点・基準・尺度」の意)を使
い、政策、施策の目標を客観的な指標として示します。また、実績の評価に
あたっては、市民の視点に立って客観的かつ適切に行われるよう、市民の参
画による評価システムを整備します。
政策評価への市民参画の推進
*

40
少子高齢化など社会構造の急速な変化
や市民の価値観が多様化する中で、地域
における相互扶助機能は弱体化し、市民
相互の社会的なつながりも希薄化してい
ます。
地域では、高齢者介護における老々介護、
独居老人に係わる事件や事故、障がい者
の自立や社会参加の難しさ、ひきこもり、
子育て家庭の孤立、児童虐待の増加など
の切実な問題が起こっており、これら福
祉の問題は誰にとっても起こりうる身近
なものとなってきています。
このような状況の中、さまざまな福祉
課題を解決するために、公的な福祉サー
ビスを拡充するとともに、NPO、ボラ
ンティアなど市民が主体的に参加するふ
れあいや助けあいなどのきめ細かい福祉
活動、すなわち地域福祉の推進は欠かせ
ません。また、市民、事業者、行政が各々
の特性と能力を理解しながら、それぞれ
の役割を担っていく必要があります。
●地域福祉計画の策定、推進
●(仮称)南部保健福祉センターおよび南部老人福祉
センターの総合的な検討に基づく整備
●(仮称)東部保健福祉センターの整備
●ボランティア車両の拡充
●交通バリアフリーの推進
●コミュニティバス等運行支援
●市営住宅の建替に伴うバリアフリー化
●介護相談員の派遣
●「(仮称)元気な高齢者づくりプログラム」の策定
と各種高齢者生活支援
●基幹型在宅介護支援センターの設置および地域型
在宅介護支援センターの拡充
●精神障がい者地域生活支援センター(兼生活訓練
施設)の整備促進
●障がい者地域生活相談窓口の開設
●障がい者の一般就労に向けた訓練や福祉的就労の
場の確保
●グループホーム、ふれあいホームの整備促進
●ユニバーサルウォークラリー等スポーツ・レクリ
エーション活動の推進
政策課題
1政策課題
1地域で支えあう 福祉施策の推進地域で支えあう 福祉施策の推進
地域社会は、住民の融和だけでなく、地域における福祉、保健、医療の存在
があって、はじめて成り立つといわれており、この新しい方向性への根幹とな
る地域福祉計画を策定します。
また、地域福祉推進に対する基盤整備への行政支援として、特に高齢者およ
び障がい者への施策を重点的に展開します。
課 題
解決に向けたてこ入れ
■主な対応事業

41
子育てに伴う経済的・精神的・肉体的
負担感や晩婚化などから、少子化が進行
しています。
少子化は、子ども同士の交流機会の減
少により子ども自身の社会性への影響が
懸念され、ひいては、労働力人口の減少
による都市の活力低下、社会保障負担の
増大など、将来に深刻な影響をもたらし
ます。
このため、子育てに喜びや楽しみを感じ、
安心して子どもを産み育てることができ
る環境づくりが求められています。
また、子どもの能力に応じた教育、障
がいのある子どもたちもいきいきと学べ
る教育環境を整えていく必要があります。
子どもたちは、未来の市原市を元気に
する主役であり、私たちにとってかけが
えのない「宝」です。すべての子どもた
ちの幸せを願い、これらの課題解決に向
けて学校と家庭、地域が連携して、子ど
もたちを健やかに育む社会が形成される
よう、横断的な施策展開を図っていく必
要があります。
●乳幼児医療費助成制度の拡充
●特別保育の拡充
●病後児保育の拡充
●認可外保育への補助
●ファミリーサポートセンターの設置
●地域子育て支援センターの拡充
●保育所待機児童解消対策の推進
●つどいの広場事業の拡充
●放課後児童健全育成事業の推進
●幼児教育振興計画策定
●学校施設の新増改築
●学校施設環境整備事業の推進
●学校給食共同調理場の整備
●小学校低学年少人数学級の推進
●小学校少人数授業の推進
●学級補助員の拡充
●読書教育指導員の拡充
●スクールカウンセラーおよびアシスタントの拡充
●教育相談事業の拡充
政策課題
2政策課題
2子育て支援と 責任ある教育の推進子育て支援と 責任ある教育の推進
子育てへのアドバイスやサポート体制、さらには市独自の施策を展開すると
ともに、すべての市民が公平にサービスを享受できるように配慮します。
また、子どもたち誰もがきめ細かな教育を受けられるよう、環境整備の充実
に向けた施策を展開します。
課 題
解決に向けたてこ入れ
■主な対応事業

42
資源・エネルギー大量消費型のライフ
スタイルは、生活に利便性をもたらして
きた一方で、環境への負担を高め、地球
温暖化をはじめ地球規模での環境の劣化
が深刻なものとなっています。また、私
たちの身近なところでは、不法投棄、自
然や生態系の破壊、環境汚染などが問題
となっています。
これらの環境問題の多くは、家庭など
における日常生活や、通常の事業活動に
よるものであり、社会経済のあり方その
ものに起因すると言えます。
� このため、経済社会の豊かさを維持
しながらも、環境への影響をできる限り
少なくなるような社会、すなわち環境の
保全と経済の活性化を同時に実現する社
会へと変えていくことが必要です。
臨海コンビナートにおいては、中長期
的な温室効果ガスの大幅な排出削減に向
け「水素社会」など脱温暖化社会をめざ
した取り組みが始まろうとしています。
これにあわせ、地域レベルでの環境保
全に対する市民活動も高まりつつあり、
先人が培ってきたこの緑豊かな自然環境
を次世代へ引継ぐためにも、これら地域
資源を活用し、人と自然がともに輝くま
ちづくりを進めていく必要があります。
●新エネルギーシステム構築に向けた条件整備
●環境学習の充実(自然体験・観察会の充実、地球
温暖化防止の啓発、こどもエコクラブ支援、低公
害車の普及啓発など)
●生態系保全活動団体の支援
●森林の保全
●里山保全管理
●3R推進事業(ごみ減量運動の促進、資源回収事
業の促進、生ごみの再資源化)
●不法投棄防止、環境美化関連事業
●環境にやさしい農業の推進
●汚水排水処理の促進(公共下水道、農業集落排水、
合併処理浄化槽)
政策課題
3政策課題
3環境にやさしい持続的発展可能な社会の構築環境にやさしい持続的発展可能な社会の構築
市民の誰もが、豊かな自然を常に享受できるような環境の再生を図る上で、
市民一人ひとりの理解と実践行動が必要です。
このため、幼児の頃からの環境意識の醸成はもとより、あらゆる環境資源を
活かし、環境と経済が好循環する持続発展可能な社会を構築するためにも、環
境モデル都市をめざします。
課 題
解決に向けたてこ入れ
■主な対応事業

43
平成15年における本市の人口千人当
たりの犯罪件数は、34.2件と県下ワー
スト4位です。犯罪は、市民生活に直接
的な脅威を与えており、早急に対策を講
じなければなりません。
しかし、これからは行政の対策だけで
は十分とは言えず、地域の強い結束が不
可欠です。このため、コミュニティ活動
を通して市民と行政がそれぞれの役割の
もと、安心できる生活を取り戻す必要が
あります。
また、交通事故の防止および市民の利
便性の向上を図るため、交通安全施設や
道路網の整備も重要です。特に都市活動
軸として欠かせない平成通りなどの主要
路線の整備を優先して進めていく必要が
あります。
さらに、施設整備にあたっては、誰も
が快適に暮らすことのできるユニバーサ
ルデザインの考え方に立った整備が求め
られています。
政策課題
4政策課題
4市民が安全・安心して 暮らせるまちの実現市民が安全・安心して 暮らせるまちの実現
市民が安全に、安心して暮らしていくため、今後も都市基盤整備を一層推進
していくとともに、住民の生命に関わる施策については積極的に展開します。
また、高齢者等の生活行動範囲の拡大や安全・安心に向けた整備に配慮して
いきます。
課 題
解決に向けたてこ入れ
■主な対応事業
●自主防犯組織支援事業
●防犯灯、街路灯の設置
●安全パトロールの実施
●歩道・点字ブロック整備事業
●交通安全指導と事故防止の啓発事業
●道路の整備
●河川の整備
●雨水排水施設の整備
●橋梁・トンネル・崖地改修事業
●木造建築物耐震改修の促進
●市営住宅の建替
●土地区画整理事業
●水道断減水対策、未給水地区解消事業
●消防施設・車両等の充実
●救急医療体制の充実

44
活力ある地域経済は、地域の発展の重
要な基盤であり、また、安定した就労機
会の存在は、市民の定住指向の大きな要
因を占めています。
本市は、これまで臨海部の石油化学産
業を中心とした企業群に支えられ発展し
てきましたが、国際的な競争が激化して
いる今日の経済情勢下では、産業基盤の
重層化を図っていくことが求められてい
ます。
農林業では、減反、後継者不足などに
伴い、田畑の荒廃が進み、大変大きな問
題となっています。本市の農業の将来を
見据え、認定農業者をはじめとする担い
手の育成支援を進めるとともに、従来の
農業従事者に加えて、新しい経営形態の
導入や、首都圏という大消費地にある立
地条件を活かした高収益の都市近郊型農
業への転換が大きな課題です。
商業については、郊外型店舗の出店な
どによる市内における商業機能の変化へ
の対策が必要となります。
●五井駅東口整備構想の具現化
●中心市街地活性化の推進
●新エネルギーシステムの構築に向けた条件整備
●臨海工業地域の機能強化
●新産業立地の促進
●人材・技術の活用による中小企業への支援
●地産地消の推進
●トレーサビリティの導入支援
●グリーンツーリズムの推進
●ブランド産品の振興
●ふるさとハウス整備の推進
●(仮称)市原南IC周辺活性化への支援
政策課題
5政策課題
5
市原市の元気を取り戻すには、経済の活性化が重要です。
このため、臨海企業や中小企業が連携して今日まで培ってきた技術開発力や
人的資源などを活かして相互の機能強化を図ります。
また、農林業の活性化に向けて経営の安定化や地産地消、観光農業などの施
策を展開するとともに、まちづくりの観点から中心市街地等の商業の活性化を
図ります。
課 題
解決に向けたてこ入れ
■主な対応事業
地域経済の活性化

45
地方分権の推進、経済成長の停滞、市
民参加意識の高まり等、これまでの行政
主導の仕組みから市民と行政との協働に
よる地域主導のまちづくりへと時代が動
いています。その中で、市自らも従来の
枠組みにとらわれない柔軟な対応が求め
られています。
一方で、少子高齢化や低経済成長のも
とで、市財政の運営は一層その厳しさを
増すことが予想されています。
本市では、これまでまちづくりへの住
民参加の基盤をなす情報公開制度の整備や、
市民の声を聞く場として地区懇談会の開
催などに取り組んできました。今後も引
き続き、より広い市民の声を市政に反映
させる仕組みの充実を図っていくとともに、
多様化する行政需要や社会情勢の変化に
柔軟に対応していくため、行財政改革を
引き続き進め、行財政運営のより一層の
効率化を図っていく必要があります。
●地域高度情報化の促進
●地域情報サイトの構築
●市民活動支援サイトの設営
●電子市役所の推進
●情報公開の推進
●各種媒体による広報活動の充実
●ティータイムミーティングの開催
●行政評価システムの導入・推進と市民参画
●バランスシートの作成、財政白書の作成
●職員の意識改革、CS運動の推進
●市民意識調査
政策課題
6政策課題
6
高度情報通信技術の活用など行政運営の簡素化、効率化を図るとともに、市
民にわかりやすく、親しまれる市役所づくりを進めます。
財政運営については、社会経済の動向を的確に把握し、緊急性や必要性など
の優先順位をもとに計画的な事業の実施に努めるとともに、民間活力を積極的
に活用します。
課 題
解決に向けたてこ入れ
■主な対応事業
行財政改革の推進

46
価値観やライフスタイルの多様化に伴い、
従来の行政主導のまちづくりの仕組みは
限界にきています。また、地方分権の必
要性がますます高まってきています。地
方分権のねらいは、単に国や県から市町
村への権限移譲ではなく、地域で考え、
地域で行動する社会づくりです。
今後、ますます厳しい行財政環境の下
では、常に公平性、中立性を求められる
行政が、多様化するすべてのニーズに十
分対応できるかどうかが問われています。
これからは、行政だけで解決できない
多種多様なニーズに対応するため、一層
の市民との協働による市政運営が不可欠
となってきます。このため、個々の市民、
市民公益活動を行う団体、事業者がお互
いの存在を理解、尊重し、役割を分担し
ながら、対等の立場で連携・補完しあい、
それぞれが自らの知恵と責任において行
動することによって、地域課題を主体的
に解決していくことが求められます。
�市民まちづくり事業の促進
�協働のためのルールづくり
�市民活動中間支援組織の検討
政策課題
7政策課題
7市民による まちづくりの推進市民による まちづくりの推進
市民と行政とのパートナーシップの確立に向け、そのきっかけとして市民自
ら取り組める事業の創出と実践を計画の新たな概念として位置づけ、その展開
を図ります。この取り組みに対する意識は大切であり、今後、公共領域の分野
においても新たな公民パートナーシップによるサービス向上につなげていきま
す。
課 題
解決に向けたてこ入れ
■主な対応事業